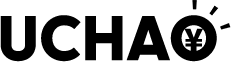公開日: |更新日:
二世帯住宅の登記に関する
注意点
このページでは、二世帯住宅を相続した場合に注意すべきポイントについて詳しく解説しています。二世帯住宅の相続には、小規模宅地等の特例を適用できるケースがあるため、対象となるか確認しましょう。
小規模宅地等の特例が適用されない
可能性がある
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税が大幅に軽減されるようになるため、不動産相続におけるメリットとして注目されています。
ただし小規模宅地等の特例でカバーできるのは、あくまでも「小規模宅」。面積の上限として、最大330㎡以下と設定されているのもポイントです。
小規模宅地等の特例を使える人とは?
小規模宅地等の特例を申請できるのは、被相続人の配偶者と、被相続人と同居の親族、さらに一定条件において同居をしていなかった人々なども指定されます。
小規模宅地等の特例が適用されない
場合がある?
小規模宅地等の特例の適用は、あくまでも一定の条件を満たしていることが前提となります。
小規模宅地等の特例が適用となる前提条件は、以下の通りです。
- 同じ棟の建物に親と子が住んでいる
- 建物の敷地の名義が親である
- 子供がその部屋を無償(家賃を払っていない)で親から借りている
- 申告期限(被相続人の死亡後から10ヶ月以内)までに所有者として居住開始
例えば、被相続人である親と相続人にあたる子が同居していなかった場合、小規模宅地等の特例として認められません。
小規模宅地等の特例を活用するメリット
小規模宅地等の特例を活用するメリットとして、相続税を大幅に減額できる点が挙げられます。
相続した不動産に関して、どれくらい相続税を支払う必要があるのか事前に確認できます。その際に基準となる価格が土地の評価額。
例えば自宅の評価額が1千万円だった場合、小規模宅地等の特例を適用できれば、最大800万円を相続税の課税対象から控除することが可能です。相続税の課税対象は残りの200万円に課せられ、相続者の負担を軽減できます。
二世帯住宅において小規模宅地等の
特例が適用される条件は?
小規模宅地等の特例が適用される
前提条件と減額割合
二世帯住宅の場合、親と子がそれぞれどの階に暮らしているか、家の中にある設備や間取りなどの条件によって、小規模宅地等の特例が適用されるか決まることを忘れてはいけません。
事業用地の場合は、土地として使っている部分に関しては50~80%、最初から自宅として使っていた土地に関しては80%の減額になります。
二世帯住宅における暮らし方のケース
非分離型
非分離型の二世帯住宅とは、一軒家の1階に親世帯、2階に子供世帯が暮らしており、家の中にある階段や廊下を使って互いの生活空間内に入っていける物件を指します。
分離型(完全分離型)
分離型の二世帯住宅とは、一軒家において1階が親世帯、2階が子供世帯になっている上、各階の入口がそれぞれ別に設けられている物件のこと。分離型の場合、同じ建物といっても二世帯の生活環境は隔絶されているため、子が親へ会いに行くためには外付けされている階段を使用することになります。
非分離型よりも分離型において
特例が適用されやすい
小規模宅地等の特例が適用されやすい物件は「分離型」の物件であると言われています。非分離型の場合は二世帯住宅なのか、単に二階建て住宅に親子が住んでいるだけなのか、適切な判断が難しいためです。
しかし完全分離型の物件でも、さらに親と子がそれぞれの専有部分を区分所有登記していた場合、それは「別の家」に暮らしていたものと見なされるため、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
区分所有登記されていない建物は
適用される
区分所有登記をされていない建物の方が、小規模宅地等の特例も認められやすい傾向にあります。
区分所有登記とは、同じ建物であってもそれぞれの部屋について別々の登記があるような建物。例として複数の住人が各階・各部屋に暮らしている集合住宅やマンションなどをイメージすると良いでしょう。
小規模宅地等の特例において重要なポイントは、親と子が同じ棟の物件に暮らしていることです。
仮に1階部分と2階部分が完全分離している二世帯住宅があったとして、さらに1階については親が区分所有登記を行い、2階については子が区分所有登記しているとします。このような場合、親と子は別々の家に暮らしていると考えられるため、小規模宅地等の特例は適用されません。
二世帯住宅が小規模宅地等の特例の
適用となるケースを確認
適用されるケース
二棟の建物が内部で繋がっていて
建物が共有登記されている場合
建物が内部でつながっている非分離型の二世帯住宅であり、その建物について親子が共有者として共有登記をしている場合、親と子は実質的に同居していると判断されるため、小規模宅地等の特例の適用が可能です。
ただし小規模宅地等の特例の適用には、複数の条件が設定されており、それらにも合致していなければなりません。
二棟の建物が内部で繋がっていない
親の単独登記の場合
それぞれの建物が内部でつながっていない分離型の二世帯住宅であったとしても、建物自体が親の単独登記であった場合、子は親から無償で子世帯部分を借りていると考えることができます。
建物の内部がつながっていない分離型の二世帯住宅であっても、他の条件と合わせることで小規模宅地等の特例の適用が可能です。
分離型で建物の登記自体がない場合
分離型の建物であり、親と子がそれぞれの居住空間を建物内部で自由に行き来できないとしても、登記自体が完了していない物件であれば、改めて親が物件の単独登記をすることで小規模宅地等の特例を適用できるようになります。
適用がされないケース
建物を増築して行き来できないが
区分所有登記されている
一世帯住宅だった建物を増築して増築部分に子が暮らしている場合、親子は互いの居住空間への行き来が不可能です。そのため、それぞれが区分所有登記していると別々の家に暮らしていると判断され、小規模宅地等の特例が適用されません。
異なる建物を渡り廊下で繋げた場合
それぞれ独立している建物があったとして、両者の間を渡り廊下で接続したとします。この場合、建物内部でつながっているわけでなく、あくまでも別々の建物という認識になるため、小規模宅地等の特例は適用されません。
区分所有登記された二世帯住宅を同一登記にする方法と利用の際の注意点
区分所有登記されている物件であっても、相続が開始されるまでに区分所有登記を解消して親の単独登記や、親子の共有登記に再申請することで、小規模宅地等の特例を適用できる可能性が高まります。
ただし、小規模宅地等の特例が適用される条件にある「物件の登記や物件構造」だけでなく、他にも設定されている条件も満たしていなければなりません。
単独登記や共有登記にしても、必ず小規模宅地等の特例が適用されるわけではないと認識しておきましょう。
二世帯住宅の小規模宅地等の特例にはプロの知恵が役立つ
二世帯住宅の小規模宅地等の特例には、不動産相続や登記に詳しいプロの手を借りることが賢明です。
自分の暮らしている二世帯住宅の現状がどうなっているか、個人で確認する場合は法務局で登記事項証明書の取り寄せが必要になります。
もし区分所有登記であった場合、単独登記や共有登記といった方法も検討できますが、それ以前に物件の構造や間取りなどもチェックしなければなりません。その他の条件に応じて求められる手続きや方法が変わってくるため、手順の明確化が難しくなるでしょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。