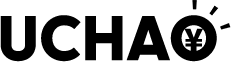公開日: |更新日:
未登記建物とは?相続したらどうすればいい?
このページでは、未登記建物が相続対象となった場合のポイントや、未登記建物を含めた遺産分割協議の注意点などをまとめて解説しています。
そもそも未登記の建物とは?
登記とは?
登記とは、不動産について誰がその所有者であるのか公的に登録するための制度です。例えば不動産の所有者には固定資産税などの税金が課せられますが、不動産は現時点で建物に暮らしている人が物件の所有者であるとは限らず、正しく誰が所有者であるのか確認しておく必要があります。
そのため、土地や建物の所有者が登記所へ申請して、自分が不動産の所有者であることを示します。
なお、所有者やその法的に認められる代理人によって登記が行われると登記記録が作成されて、その不動産が誰に所有されているのか記録されるという仕組みです。
建物の登記が済んでいるか確認する方法
一般論として、固定資産税の納税通知書が送られてきた場合、対象不動産が未登記であれば通知書に「未登記」と記載されていたり、家屋番号が記載されるべき欄が空欄であったりします。そのため、固定資産税の納税通知書を確認すれば物件が登記済か未登記か判断することが推察です。
ただし例外的に、家屋番号が納税通知書に記載されているものの、実際には未登記という不動産も存在します。
そのため、不安が残るようであれば法務局で建物の登記簿を閲覧することも必要です。登記が適切に済んでいない物件であれば、当然ながら登記簿の閲覧申請を行っても「該当なし」などの返答になる可能性が高まります。
不動産を未登記にしておくことは違法
未登記のまま放置することは違法
不動産登記法によって、例えば建物を新築した場合、所有者は所有権を取得したタイミングから1ヶ月以内に「表題登記」の申請を行わなければならないと定められています。言い換えれば、表題登記が正しく完了していなければ登記記録が存在しないことになり、その物件は未登記建物という形になることがポイントです。
未登記を放置することは違法なのに未登記建物がある理由
表題登記とは新築物件を初めて登記することを指します。通常、不動産ローンなどを組んで物件の新築を行う場合、物件の書類を正しく用意する上で登記が行われます。しかしローンを利用せずに自宅を新築したような場合、表題登記を行わないまま自宅で生活するといったこともシステム上は可能です。
未登記建物であっても相続対象になる
建物の所有者が死亡した場合、相続権を有する人間が相続人として建物を引き継ぐことになります。そしてそれは未登記建物であっても同様です。
相続対象はあくまでも遺産であり、不動産として価値がある建物ならば登記の有無にかかわらず相続対象となります。
なお、2021年4月に改正法が成立し、相続人が建物を相続した場合、定められた期限までに相続登記を行わなければならなくなったことも重要です。
未登記建物を相続する際に行わなければならないこと
相続人による表題登記
繰り返しになりますが、建物を未登記のまま放置することは違法です。加えて、相続人は相続が不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があると、改正法によって定められていることにも注意してください。
このような理由から、相続人が未登記建物を相続したような場合、改めて相続人が未登記建物の新しい所有者として表題登記を行うことが必要となります。
なお、表題登記を行わないからといって相続税の対象から不動産を除外できるといったことはありません。
表題登記の義務を怠ると過料に処される
表題登記の申請義務を怠り、相続後も未登記建物のまま放置すれば、法的には違反者として「10万円以下の過料」に処される可能性があります。
表題登記と所有権保存登記
表題登記とは建物について公的に登録し、物件の所在地や家屋番号、建物の種類や構造などの項目が登記記録に記載されることを指します。
一方、所有権保存登記とは、対象となる不動産が誰の所有物であるのか公的に記録する申請です。
一般的に登記といえば、表題登記と所有権保存登記をまとめて指すことが多いものの、実際には表題登記と所有権保存登記は別の申請であることがポイントです。
所有権保存登記は通常、表題登記と同時に行われます。
所有権保存登記を行っておかなければ、自分が不動産の所有者であることを公的に明治できないため、例えば金融機関で不動産を担保としてローンを組んだり、第三者と不動産の所有権について訴訟対決になった際に自分が所有者であると主張したりといったことができません。
なお、所有権保存登記を行う際には登録免許税を支払うことが必要です。
未登記建物を登記せずに放置するデメリット
登録免許税の支払いを回避しようと、所有権保存登記をせずに済ませようとする人もいます。しかし、未登記建物のまま放置することは様々なデメリットを生じさせることが重要です。
未登記建物をそのままにしておくデメリットとしては、所有者として公的に証明できなかったり、金融機関で不動産を担保にできなかったりする他にも、税制上の優遇措置を受けられずに固定資産税が高くなったり、不動産の売買ができなかったりと、複数のものが挙げられます。
また、長年にわたって固定資産税を支払っていなかったような場合、過去にまでさかのぼって固定資産税を一括請求される恐れもあるでしょう。
未登記建物も遺産分割の対象になる?
未登記建物も相続財産には違いない
前述したように、表題登記が行われていない未登記建物であっても、資産として価値があれば相続財産に含まれます。
相続財産に含まれるということは、遺産分割協議において議論すべき対象になるということです。
ただし、未登記建物には物件の売買ができないといったデメリットがあり、例えば未登記建物を売却して現金化し、それを遺産として分割するなどの提案も認められません。
未登記建物の遺産分割協議の進め方
遺産分割協議において未登記建物の扱いが議論される場合、必ずしも表題登記を行ってから遺産分割協議に入らなければならないということはありません。ひとまず未登記建物として扱い、遺産分割協議によって建物を相続する人物が定まってから、改めて表題登記や所有権保存登記を行うことも可能です。
しかし、所有権保存登記が完了していなければ遺産としての処理の仕方に制限が生じてしまうため、現実には先に被相続人名義で物件の登記を行っておき、その後で遺産分割協議へ入って実際の所有者を決定するといったケースも少なくありません。
未登記建物について遺産分割協議書を作成する際に注意するポイント
遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産について正しく財産目録へ記載しておくことが必要です。
一方、未登記建物は公的に存在や所有者が定められておらず、登記記録の内容を転記する形で財産目録を作成することができません。そのため、固定資産評価証明書や名寄帳といった書類に記録されている内容をまとめた上で、さらに「未登記」などの表記を行って未登記建物であるということを明示しておきます。
まとめ
未登記建物を相続する場合であっても、相続人の間で遺産分割協議が必要であることに違いはありません。しかし、未登記建物が相続財産になっている場合、通常の遺産相続よりも考慮しなければならない点や、必要とされる手続きの種類が異なってくるため、未登記建物の取り扱いや相続制度に詳しいプロへ協力を求めることが無難です。
未登記建物の登記を誤れば過料に処されることもあるため、スムーズな相続を完了できるように専門家へ相談しておきましょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。