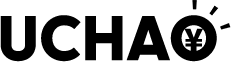公開日: |更新日:
夫婦共有名義不動産は離婚したらどうなるの?
このページでは、離婚による夫婦共有名義の不動産の扱いについて紹介しています。
最近では、夫婦共働きの家庭も多く、共有名義での不動産購入をするケースも少なくありません。もしもの離婚に備え、共有持分である不動産をどのように対処すべきかをあらかじめ学んでおくことがおすすめです。
離婚後の共有不動産を放置するとどうなる?
共有持分とは
共有持分とは、不動産の所有権を持つ者それぞれが登記上で有する権利割合のこと。たとえば購入費用を6:4で負担した場合、登記簿にも同じ比率で記載され、自分の持分部分は第三者に単独で売却や譲渡が可能です。
離婚後の共有名義不動産が抱えるリスク
離婚に伴って不動産の名義を夫婦のままにしておくと、後々のトラブルやコスト増大を招きかねません。関係が破綻した相手と再び協議を重ねる必要があるほか、放置するほどリスクが膨らむため、早めの対処が大切です。
活用の制限
共有名義の不動産は、自分一人では売却も長期賃貸も行えず、共有者全員の合意が必要になります。たとえリフォームや短期の賃貸契約であっても、相手の共有持分が過半数を超えていれば同意が得られず、管理行為すら制限されるケースが少なくありません。その結果、活用プランが思うように進まず、時間経過とともに資産価値が下落する恐れが高まります。
精神的な負担も無視できず、交渉がこじれれば調停や訴訟に発展する可能性もあるため、早期に共有状態の解消を検討すべきでしょう。
住宅ローン違反
住宅ローン契約の多くは「契約者本人が居住すること」を前提としており、共有名義で離婚後に住まない配偶者がいる状態が続くと、契約違反と見なされる恐れがあります。
金融機関に無断で使用状況が変わると一括返済を求められる可能性があり、また連帯債務型ローンでは、共有相手が返済を滞らせた場合にも残された共有者に支払い義務が及びます。支払いが滞ると競売にかけられ、市場価格を大きく下回る価格で売却されるリスクもあるため、離婚時に返済計画や名義の整理方法を明確にしておくことが不可欠です。
相続トラブル
共有名義のまま長期間放置すると、将来の相続時にさらなる共有者が加わり、権利関係が著しく複雑化します。たとえば元配偶者が再婚し、その相手や再婚相手の子どもが法定相続人となると、赤の他人と共同所有する事態も想定されます。新たな共有者との協議は困難を極め、固定資産税や管理費の支払い調整でトラブルに発展しやすくなります。場合によっては相続人同士の意見対立が共有物分割調停や訴訟に発展し、解決までに多大な時間と費用を要することもあるため、離婚時点での共有解消が望ましいでしょう。
住み続ける場合に注意したいこととは?
共有名義の不動産に離婚後も住み続ける場合、住宅ローンの名義変更が原則認められない点には特に注意が必要です。金融機関は返済能力を再審査したうえでしか名義変更を受け付けず、多くの場合「借り換え」によって一括返済と新規契約を行う必要があります。
この手続きでは単独での返済能力や信用力が厳格に審査され、要件を満たさないと借り換え自体が難しくなることがあります。また、固定資産税や都市計画税、修繕積立金などの維持費は所有し続ける限り発生し続け、住まない共有者が支払いを渋る場合は全額自己負担となるリスクも高まります。
さらには、長期にわたり元配偶者との連絡が途絶えると、賃貸や売却時に同意を得られず、突然売却計画が頓挫する可能性があるため、事前に公正証書で取り決めを行い、合意内容を法的に残しておくことをおすすめします。
離婚後の共有持分を売却する方法
相手(元配偶者)に売る
最もオーソドックスな手法。まずは元配偶者に持分を買い取ってもらい、単独所有に切り替えます。まとまった現金が要ることと、住宅ローンをひとり名義へ借り換える交渉が必要となる点に注意してください。
共有物分割請求で現物分割や競売をする
協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ共有物分割請求訴訟を提起。物理的に分割(現物分割)できない場合は売却して分配(換価分割)、または代償分割と呼ばれる一方が買い取る方法を選択します。
共有持分の買取専門業者に売る
共有持分のみでも、民法206条(*1)・249条(*2)により「自己の持分は自由に処分できる」と明文化されています。そのため相手方の同意不要で、不動産買取専門業者へ持分だけを売却可能です。
参照元:(*1)https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC206%E6%9D%A1 (*2)https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC249%E6%9D%A1
- ウェブ・電話で無料査定依頼:住所や持分割合などを伝えると相場感がわかる。
- 必要書類を提出:登記事項証明書、固定資産税評価証明書、本人確認書類を用意。
- 現地調査と法務チェック(1~3日程度):権利関係や建物状況を確認し、正式な買取額を提示。
- 売買条件の確定・契約締結:価格・決済日を確定し、契約書にサイン。
- 決済・登記手続き(最短即日~1週間):代金受領後、司法書士が持分移転登記を完了します。
買取額は不動産全体価格の40~70%程度が一般的ですが、複数社の査定を比較することでより納得感のある金額を引き出せます。
実際に揉めるケースとその予防策
売却後に元配偶者から「知らされていない」と請求されないよう、契約前に内容証明郵便で売却意思を正式通知。契約書には「補償免責条項」を盛り込み、売却後の紛争リスクを限りなく抑えましょう。
共有持分の買取専門業者へ売却するメリット
不動産業者が買取できない共有持分を売れる
一般の不動産会社は、共有持分単体の取引に慣れておらず、“取扱リスク”や“流動性の低さ”を理由に買取を断ることが少なくありません。特に建物の残存価値や権利関係の調査に手間がかかるため、売り手・買い手双方の利益を確保しづらいのです。
一方、共有持分の買取専門業者は、離婚や相続などの複雑案件を多数手がけてきた実績があります。社内に司法書士や弁護士を抱え、権利関係のクリアリングを迅速に行えるため、共有持分だけでも安心して売却可能。独自の投資家ネットワークや自社買取スキームを活用し、一般業者では実現しにくい「売却~決済」のスピード感と安定性を両立しています。
トラブルや揉め事を回避できる
万一、売却後に元配偶者や相続人から請求やクレームが発生しても、専門業者であれば契約段階から「免責条項」や「補償規定」を盛り込んだ契約書を作成します。また、弁護士・司法書士と連携しているため、権利関係の再確認や事前のリスク洗い出しを徹底。トラブルが予測されるケースでは、事前に和解協議や代償分割の提案を行い、訴訟まで発展しないようワンストップでフォローしてくれます。
無料査定・スピード対応・秘密厳守などの対応ができる
-
無料査定
Webフォームまたは電話で持分の住所・登記情報・負担割合を伝えるだけで、専門スタッフが相場を即時算出。面談不要でメールやLINEでも結果が受け取れるため、忙しい方も手軽に始められます。 -
スピード現金化
必要書類が全て揃えば、通常1~3日以内に契約締結、その後最短即日で決済可能。急な生活資金や引っ越し資金の手当てにも対応できる柔軟性があります。 -
秘密厳守
社内の個人情報保護基準に基づき、オンラインポータルでのデータ管理やNDA(機密保持契約)の締結により、近隣や勤務先、元配偶者に知られずに手続きを完了できます。
共有持分の買取業者を選ぶポイントと注意点
安心して任せられる業者の特徴とは
-
取引実績の明示
年間○○件以上の共有持分買取実績をウェブサイトに公開。具体的な事例紹介やビフォー・アフター価格を掲載している業者は、透明性が高く安心です。 -
高い顧客評価
Googleレビューや住宅情報サイトの口コミで、評価★4.0以上を維持しているかをチェック。個別のコメントに目を通し「対応スピード」「担当者の説明力」「アフターフォロー」なども確認しましょう。 -
法務体制の充実
司法書士・弁護士が社内常駐または提携し、権利関係調査や登記手続きをワンストップで対応できるか。別途外部委託が必要な場合は、手数料やスケジュールへの影響を事前に確認してください。 -
アフターサービス
売却後のトラブル発生時に備えた「補償制度」や、再売却サポート、相談窓口の有無をチェック。売却後も安心して任せられる体制が整っていることが重要です。
悪質業者を見抜くチェックポイント
-
極端な査定額
相場より大幅に安い・高い査定額はマージン調整や未公開コストを上乗せしている可能性あり。複数社比較で適正価格を把握しましょう。 -
不透明な手数料
「別途費用」や「追加手数料」が曖昧に記載されていると、契約後に想定外の請求をされる恐れがあります。見積書は項目ごとに内訳を確認してください。 -
契約解除の条件
一方的な解除権や過度な違約金条項が含まれている場合、トラブル時に不利になります。契約書の「解除条項」は必ずチェックを。 -
問い合わせ対応
電話やメールでの初期応対が遅い・あいまいな返答が続く場合は、その後の手続きでも同様の不安が残ります。レスポンスの速さと丁寧さを重視しましょう。
共有持分を売却するまでのステップ
必要な書類や準備
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 住民票または戸籍附票
- 内容証明郵便の控え(売却通知用)
査定〜契約までの流れ
- 無料査定依頼
- 現地調査・法務チェック
- 条件調整
- 契約締結・決済
ローンが残っている場合
売却代金で一括返済が難しいときは、借り換えや連帯保証人変更の手続きを金融機関と協議。場合によっては抵当権抹消費用や保証料の見積もりを事前に確認してください。
売却完了までの期間・費用・税金の情報まとめ
最短で売却完了までの所要期間
専門業者利用で書類不備がなければ2週間程度、通常は1〜2ヶ月を目安に進行します。
手数料・仲介料・登記費用の相場
- 査定料・仲介手数料:無料~売却額の3%程度
- 登記費用:2〜3万円前後
- 内容証明郵便費用:1通あたり約1,500円
売却益にかかる税金と節税できるケース
- 譲渡所得税:所有期間5年以下で約39%、5年超で約20%
- 必要経費:司法書士報酬や広告費は譲渡所得の経費計上が可能。確定申告で節税を図りましょう。
持ち分の売却は専門業者への相談を第一歩に
離婚に伴う共有持分の売却は、まず専門業者への無料査定依頼から始めましょう。複数社の査定額や対応スピード、サポート内容を比較することで、ご自身の状況に最も合った業者を見つけられます。専門家ならではのノウハウを活用し、価格交渉や書類手続きの不安を解消しながら、安心して売却を進めることが可能です。
次に、東京エリアで実績豊富・ 評判の高い共有持分買取業者を厳選してご紹介します。売却の成功率アップを目指す方は、ぜひ「東京でおすすめの共有持分の買取り業者もチェック」をご覧ください。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。