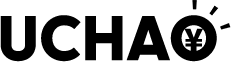公開日: |更新日:
農地の共有持分を売却する方法とは?
農地の共有持分の売却には「農地のまま売却する」方法と「地目を変更して売却する」方法がありますが、農地法の制限などがあり、売却は難しいのが現状です。ここでは、農地の共有持分を売却する方法や流れを紹介します。
農地の共有持分を売却する際に知っておきたい「制限」
農地の売却は可能ですが、さまざまな制限があり、一筋縄ではいかないのが実情です。どのような制限があるのか詳しく紹介します。
農地法による制限があり「許可」をもらう必要がある
農地の売却は、農地法によって制限されており、勝手に譲渡したり変更したりできないようになっています。なぜなら、「国民の食糧自給のためには農地が重要」とされているからです。
そのため、農地を売却する際は、農業委員会や都道府県知事に許可申請を出し、許可をもらわなければなりません。
”第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。”
”第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。”
農地を売却する場合は農業委員会の許可が、農地を「農地以外」にする場合は、都道府県知事もしくは市町村長の許可が必要です。農業委員会は市町村ごとに設置されているため、申請方法がわからない際は問い合わせてみましょう。
第三者への売却は許可されないことがある
第三者に農地を売却する場合、ケースによっては許可申請が通らないことがあります。
たとえば、AさんとBさんが農地を共有している状態で、Aさんが自分の共有持分を第三者のCさん(農業を営む人)に売却したとします。BさんとCさんには、何のつながりもありません。
こうした場合、農地はBさんとCさんで共有することになりますが、Cさんが耕作をしない可能性や、耕作物をめぐってBさんとCさんがトラブルになる可能性が考えられます。
農業委員会が農地売却の許可を出す際には、「売却された共有持分の農地が、その後どのように利用されるか」といった観点も審査対象となるため、トラブルになるおそれがあるケースの場合、売却の許可がおりないケースがあるのです。
共有者間であっても売却できないケースもある
共有者同士であっても、農地を売却できないケースもあります。たとえば、親の農地を兄弟で相続したが、どちらかが会社員である場ケースです。
農地を農地のまま売却する際は、売却相手が農業に従事している人でなければなりません。この規制は、共有者間の持分売買であっても同じです。そのため、兄が共有者である弟に農地を売却したくても、弟が会社員である場合には、持分の売却はできません。
このような場合には、共有者同士で話し合って農地全体を売却する、自分の持分を放棄するなど、ほかの方法も検討してみましょう。
共有持分のみの「農地転用」はできない
農地を住宅や駐車場など、農地以外のものにする農地転用。「自分の持分のみ、土地の用途を変更したい」と思う方もいるかもしれませんが、自分の持分のみの農地転用はできません。
共有する農地を転用する際は、自分の持分のみではなく、農地全体を転用する必要があり、転用するためには、ほかの共有者の同意が必要になります。
加えて、農地転用には2つの許可基準が設けられているため、農地の区分によって転用の許可がおりないケースもあります。たとえば、市街地にある農地は原則許可されますが、おおむね10ha以上の集団農地や、市町村によって「農用地区域」と定められた区域内の農地の転用は、原則不許可です。
農地転用を考えている場合は、農地がどの区分になっているか、あらかじめ農業委員会に確認しましょう。
農地売却の流れ
農地の共有持分の売却には、「農地のまま売却する」方法と「地目を変更して売却する」方法があるため、2つの流れを紹介します。
農地のまま売却する場合
- 1.売却相手を探す(農業従事者限定)
- 2.売買契約を結ぶ
- 3.農業委員会に許可申請をする
- 4.所有権移転登記をする
農地を「農地のまま」売却する方法です。農地のまま売却することもできますが、その際、「売却相手(買主)は農業を営んでいる人でなければならない」という制限があります。
農地を売却する際には農業委員会の許可が必要になるため、早めに申請をしておきましょう。また、ほかの共有者に売却する際であっても、その共有者が農業を営んでいない場合には、共有持分の売却はできない点を注意しておきましょう。
地目変更して売却する場合
- 1.売却相手を探す(農業従事者以外も可能)
- 2.売買契約を結ぶ
- 3.農業委員会に相談
- 4.都道府県知事または農業委員会に農地転用許可申請をする
- 5.地目変更登記をする
- 6.所有権移転登記をする
地目を「農地以外」に変更して売却する方法です。たとえば、農地から宅地に変更した後に売却するようなケースです。
農地転用と地目変更は、混同されがちですが異なります。農地転用とは、「農地を農地以外の目的に使用してもいいよ」という許可をもらうことです。そのため、許可をもらっても、登記上の地目は農地のままです。
農地を「宅地」など、ほかの地目で売却する際には、「地目変更登記」の手続きが必要になります。地目を変更してから1か月以内に地目変更登記をおこないましょう。
農地以外に変更することで、売却相手が農家という制限が外れるため、買い手がつきやすくなります。とはいえ、農地の区分によっては地目変更ができない場合もあるので注意が必要です。
農地売却で悩んだときは農地買取業者に相談してみよう
農地を売却したいと思っても、農地法による制限や手続きの煩雑さから、なかなか前に進めない方が多いのではないでしょうか。特に相続によって農地を引き継いだものの、農業を継ぐ予定がなく処分したいというケースでは悩みが尽きません。
こうした場合に頼りになるのが農地の買取を専門に行う業者です。農地買取業者に相談することで、手続きの簡略化やリスク回避が可能になり、安心して売却を進めることができます。
農地買取業者に相談するメリットとは?
農地買取業者に依頼する最大の魅力は、売却を効率的かつ安全に進められる点にあります。
農地は宅地やマンションと違い、法的な規制が多く、売却には農業委員会や自治体の許可が欠かせません。そのため、個人で売却を進めようとすると書類の準備や申請に多くの時間と労力がかかってしまいます。
専門業者に依頼することで、こうした煩雑な作業を任せられ、スピーディーに現金化できる可能性が高まります。さらに、売却後のリスクが軽減されるのも大きな安心材料となるでしょう。
スピーディーな対応で決済までがスムーズ
農地を一般市場で買い手を探す場合、購入希望者は農業従事者に限られることが多く、買い手が見つかるまでに長い時間を要するのが現実です。これに対して農地買取業者は、買い取りを前提にしているため、査定から契約、決済までの流れが格段に早いのが特徴です。
通常の不動産売却では数か月から半年以上かかることもありますが、買取業者に依頼すれば最短で数週間から1か月程度で現金化できるケースも珍しくありません。迅速な対応は、固定資産税や管理コストをできるだけ早く解消したい方にとって大きなメリットになるでしょう。
煩雑な手続きはすべてお任せできる
農地の売却には農地法第3条や第5条に基づく許可申請が必要であり、申請書の作成や役所への提出など専門的な知識が必要です。これを個人で進めようとすると、不備による差し戻しや追加書類の要求が相次ぎ、想像以上に手間取る場合が多くなってしまうでしょう。
農地買取業者に依頼すれば、こうした申請手続きや関連書類の整備を一括して代行してもらえます。専門業者は行政とのやり取りにも慣れているため、スムーズに許可取得まで進めることが可能です。手続きのストレスを軽減し、安心して任せられる点は大きな魅力です。
契約不適合責任が免除されるため売主のリスクが軽減
通常の不動産売却では、売却後に地中埋設物や境界問題などが発覚した場合、売主が一定の責任を負う「契約不適合責任」が生じます。農地の場合も例外ではなく、買主から損害賠償請求を受けるリスクがあるのです。
しかし、農地買取業者に売却する場合、契約時に契約不適合責任が免除されることが一般的です。そのため、売却後に予期せぬトラブルが発覚しても、追加の負担を負わずに済む点が安心材料となります。
特に長年放置されてきた農地や境界が不明確な土地を手放す際には、リスクを抑えて安全に現金化できるという大きなメリットがあります。
農地を高額で売却できる不動産買取業者の選び方
農地をできるだけ高値で売却したいと考えるなら、どの業者に依頼するかが極めて重要です。業者ごとに得意分野や査定基準が異なり、査定額に数十万円から数百万円の差が出ることも珍しくありません。
高額での売却を実現するためには、専門性や実績、信頼性をしっかりと確認する必要があります。ここでは、信頼できる業者を選ぶ際に押さえておきたいポイントを紹介します。
農地を専門に取り扱う不動産買取業者をピックアップする
不動産会社の中でも、農地の売却に強い業者とそうでない業者があります。農地を専門に扱う業者は、農地法や農業委員会の手続きに精通しており、適切なアドバイスを提供できます。
一般的な住宅やマンションを主に取り扱う業者では、農地特有の制約や手続きに対応できないこともあるため、専門性の高さは非常に重要です。農地専門の業者を探すことで、スムーズな手続きと高額査定を期待できるでしょう。
買取実績が豊富かどうか確認する
農地の買取実績が豊富な業者は、多様なケースに対応してきた経験を持っています。これまでに扱った事例が多ければ多いほど、特殊な条件や権利関係の複雑な案件にも柔軟に対応できる可能性が高まります。
実績のある業者は地域ごとの相場や売れやすい条件も熟知しているため、適正かつ高額な査定を期待できます。公式サイトや相談時に過去の実績を確認することは、業者選びにおいて欠かせないプロセスです。
口コミを見てみる
実際にその業者を利用した人の声は、信頼性を判断するうえで貴重な参考資料となります。口コミには対応の丁寧さやスピード感、査定額の妥当性など、公式情報だけでは分からない実際の体験談が含まれています。
特に対応の誠実さやトラブル時のフォロー体制についての評価は重要です。ただし、口コミには個人の主観も含まれるため、複数の声を参考にして総合的に判断するのが望ましいでしょう。
複数社に査定依頼を出す
一社だけの査定額を鵜呑みにしてしまうと、相場より安い価格で売却してしまう恐れがあります。そのため、必ず複数の業者に査定を依頼することが大切です。
複数の査定額を比較することで、適正な市場価格を把握できるだけでなく、業者ごとの対応力や提案内容の違いも見えてきます。査定依頼は無料で対応している業者が多いため、できるだけ多くの選択肢を持つことが高額売却への近道となります。
査定額だけではなく担当者の人間性をチェックする
農地売却は一度きりの取引ではありますが、手続きが複雑で長期にわたる場合もあります。そのため、担当者の人柄や対応力も重要な判断基準です。説明が分かりやすく、誠実に対応してくれる担当者であれば安心して取引を進められます。
逆に強引な営業姿勢や不明点をはぐらかすような対応が見られる場合は注意が必要です。信頼できる担当者に出会うことが、スムーズで満足度の高い売却につながるのです。
農地の売却相場と金額を大きく左右する3つのポイント
農地の売却価格は一律ではなく、立地条件や利用可能性によって大きく変動します。相続などで突然農地を引き継いだ場合、実際の価値がどれほどか分からない方も少なくありません。ここでは、農地の売却相場を大きく左右する三つの代表的な要素について解説します。
宅地に転用可能かどうか
農地を宅地へと転用できるかどうかは、価格に大きく影響します。宅地転用が可能な土地であれば、将来的に住宅地や商業施設として利用できるため需要が高まり、農地のままよりも高額で売却できます。
ただし、転用の可否は都市計画法や農地法によって厳しく制限されており、農用地区域に指定されている場合には転用が認められません。自治体ごとのルールも異なるため、専門家に相談して可能性を確認することが重要です。宅地化できる農地は市場価値が大幅に上がるため、査定の際には必ず確認すべきポイントといえるでしょう。
道路に面しているかどうか
農地が道路に直接面しているかどうかも価格を大きく左右します。道路に接している土地は利便性が高く、将来的な活用の幅が広がるため評価額が上がりやすい傾向にあります。
反対に、周囲が他人の土地に囲まれた「袋地」の場合は、利用が制限されるため大きく価値が下がることがあります。特に宅地転用を視野に入れる場合、建築基準法に基づき幅員4メートル以上の道路に一定距離以上接していなければ建物を建てることができません。そのため、農地がどの程度道路に接しているかは、査定額に直結する重要な要素です。
近くに電柱があるかどうか
一見すると大きな影響がないように思える電柱の有無ですが、これも査定額に影響を与える要素のひとつです。電柱や電線がすぐ近くにある農地は、宅地転用後にインフラ整備が容易になるため、買い手にとって魅力的な条件となります。
上下水道やガスなどのライフラインと同様に、電気供給のしやすさは土地の利用価値を高めます。反対に、周辺に電柱がなく新たに引き込み工事が必要な場合はコストがかさみ、査定額が低くなることがあります。インフラ環境が整っているかどうかを確認することは、農地売却において見落とせないポイントです。
農地買取業者に買い取ってもらう流れ
実際に農地を業者に買い取ってもらう場合、どのような流れで進むのかを把握しておくと安心です。基本的には査定から契約、決済までのステップで構成されており、順序を理解しておくことでスムーズに対応できます。ここでは、代表的な流れを三つの段階に分けて解説します。
1.複数の不動産業者に査定を依頼する
まず最初に行うべきは、複数の業者に査定を依頼することです。査定を通じて農地の市場価値を把握し、信頼できる業者を見極めます。複数の業者から査定結果を受け取ることで、価格の妥当性や業者ごとの対応力を比較検討できます。
査定依頼は無料で行っている業者が多いため、できるだけ多くの情報を集めることが大切です。この段階で業者の対応姿勢や専門知識も確認できるため、売却の成否を左右する重要なステップとなります。
2.買取業者と売買契約を結ぶ
査定結果や対応を比較検討したうえで、納得できる業者が見つかったら売買契約を締結します。契約時には農地法に基づく許可が必要であり、業者が代行して申請を行うのが一般的です。
契約内容には売買価格や引き渡し時期、契約不適合責任の有無などが記載されますので、必ず内容を確認して納得してから署名捺印しましょう。専門的な条項が含まれていることも多いため、不明点があれば遠慮なく担当者に質問することが大切です。
3.決済・引き渡し・所有権移転登記をする
契約後は決済と同時に農地の引き渡しを行います。売買代金が支払われると、所有権移転登記が実施され、正式に買主へと権利が移ります。この段階では司法書士が登記手続きを担当するのが一般的であり、売主は必要書類を提出すれば問題ありません。決済までが完了すれば、売主としての責任から解放され、安心して取引を終えることができます。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。