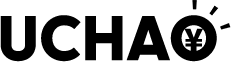公開日: |更新日:
共有持分を相続する流れとは?
相続するにあたり、「不動産の共有持分を相続したけど、どうしたらいいのかわからない」という方は少なくありません。ここでは、共有持分の相続が発生した際の流れや注意点を紹介します。
共有持分を相続する手順
共有持分の相続が発生した際の手順は、以下のとおりです。
- 相続財産と相続人を調査する
- 遺言書がないか探す
- 遺言書がなければ遺産分割協議をおこなう
- 相続登記を申請する
- 相続税を納める
相続財産と相続人を調査する
まずは相続財産と相続人を調査しましょう。相続財産は、被相続人のプラスの資産だけでなく、負債や権利義務なども含まれます。
【相続財産に含まれるもの】
- 預貯金・現金・有価証券など
- 不動産・土地・山林など
- 自動車・船舶など
- 宝石・骨董品・家財など
- 住宅ローン・借金・未払い金など
- 借地権・会員権など
ただし、養育費の支払い義務や年金の受給権など、被相続人専属の権利や義務は、相続財産となりません。通帳や保険、契約書類など一つひとつ確認していきましょう。
確認後は、「財産目録」を作成しておくことをおすすめします。財産目録を作成しておくと、相続税申告の手間が省けるほか、相続人同士の話し合いもスムーズに進められ、遺産分割協議がまとまりやすくなります。
遺言書がないか探す
遺言書がないか探しましょう。遺言書は、自宅で保管されているとは限りません。
たとえば、法務局や銀行の貸金庫にて保管している、弁護士や司法書士などの専門家が保管しているといったケースもあります。
また、公証役場にて公証人に筆記してもらう「公正証書遺言」を作成し、公証役場で保管されている可能性もあります。
公正証書遺言が作成されている場合は、公証役場の検索システムで遺言書の有無を確認できるため、確認してみましょう。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を分割するのが原則です。
遺言書がなければ遺産分割協議をおこなう
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって分割方法を話し合います。遺産分割協議で注意すべき点は、相続人全員が参加する必要があることです。
必ずしも対面ではなく、電話やメールでの話し合いも可能ですが、「遺産分割協議書」を作成するときには、相続人全員の署名と押印が必要です。全員が内容に同意していない場合、あるいは押印がない場合などは、無効になる可能性があるため注意しましょう。
遺産分割協議での話し合いがまとまらない際は、調停や裁判に進む方法もあります。
調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いで円満な解決を図る制度です。あくまでも話し合いでの解決を目的としているため、誰かが合意しなければ不成立となります。
不成立となった場合には、裁判に進み分割方法が決定されます。
相続登記を申請する
遺産の分割方法が決定したら、法務局で相続登記の申請を行いましょう。相続登記とは、亡くなった方の土地や建物の名義を、引き継いだ相続人へ変更する手続きのことです。
共有持分を取得した方が登記申請書を作成し、手続きをおこないます。申請の際には、「登記原因証明情報」「住所証明書」「評価証明書」が添付書類として必要になるため、合わせて準備しましょう。
なお、登記申請書は個人での作成も可能ですが、不備などがあると修正して再度提出しなければならず、手間がかかります。
手間や労力をかけず、スムーズにおこないたい場合には、弁護士や司法書士への依頼を検討するのも、一つの手段です。
相続税を納める
相続した共有持分には相続税がかかるため、相続税の申告をして納めましょう。申告は、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署です。
相続税の計算では、以下の手順を踏みます。
- 各相続人の課税価格を求める
- 基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を差し引く
- 求まった金額を法定相続どおりに分割したと仮定して、各相続人の「仮の取得金額」を求める
- 「仮の取得金額」から、各相続人の「仮の相続税額」を求める
- 「仮の相続税額」で求められた相続税額を合算する
- 実際の分割割合に応じて、各相続人に割り振り、課税する
計算が複雑なため、シミュレーションサイトなどを利用するのもおすすめです。
共有持分を相続するときの注意点
共有持分を相続する際には、いくつかの注意点があるので押さえておきましょう。
共有持分だけでなく「すべての相続財産」を考慮して分ける
相続する際の相続財産は、現金や有価証券、骨董品など、すべての相続財産をまとめた上で分割方法を検討し、公平に分けられるようにすることが重要です。
【例】
- 共有持分を均等に分割する
- 相続人Aが持分をすべて相続する。代わりに、相続人Bは現金を、相続人Cは自動車を相続する
- 共有持分を売却し、売却益を相続人同士で分割する など
相続では、共有持分以外の相続財産も分ける必要があります。のちのちトラブルにならないよう、「共有持分のみ」考えるのではなく、すべての相続財産を含めて考えましょう。
相続対象の不動産に住んでいても優先的に相続できるわけではない
相続対象の不動産に住んでいたからといって、優先的に相続できるわけではありません。
民法では、被相続人の財産を継承できる相続人の範囲を「法定相続人」として定めており、順位も決められているからです。法定相続人は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
たとえば、父親が亡くなり、相続人は同居している子どもAと、別居している子どもBだとします。この場合、同居しているAが優先して不動産を相続できるわけではありません。別居しているBにも同様の相続権があります。
仮に、子どもAがすべての持分を相続するのであれば、ほかの相続財産をBに分ける、あるいはBの本来の持分相当である金銭をAからBへ支払うなど、公平になるようにしましょう。
なお、「共有持分はいらないから相続を放棄したい」という方は、期限に注意が必要です。
相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」と定められています。早めに家庭裁判所へ行き、手続きしましょう。
共有持分は相続後もトラブルが起こりやすい
共有持分は、トラブルが起こりやすい側面があります。たとえば、「立て替えをしたいけど、共有者が反対している」「共有者が税金を支払わない」など、共有しているがゆえに、対立や不平不満などが起こり、トラブルが起こりやすくなってしまうのです。
共有名義は、相続後もトラブルの引き金になる可能性があるため、できれば単独での相続や売却などで、共有名義の解消をすることをおすすめします。
トラブルを避けるなら売却の検討も
誰でも、可能ならトラブルを避けたいものです。いざこざから解放されるには、共有持分を売却することも検討してみましょう。
共有持分を売却すれば、相続人で売却益を割り振れるため公平です。また、買取業者に相談すると、早ければ2日程度で売却できるところもあります。
弁護士と連携している買取業者では、共有持分で揉めているケースでも相談可能です。無料相談ができるところもあるため、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。