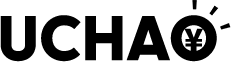公開日: |更新日:
共有持分・共有不動産と使用貸借のついて
使用貸借とは、どのようなことを指すのでしょうか。知らないままに放置すると費用負担が増えたり、不動産が借主の所有権になってしまったりする可能性があるため、早めに把握し対処することが対策を立ることが大切です。
ここでは、共有持分・共有不動産における使用貸借について、成立要件や解除要件、リスクを紹介します。
使用貸借とは?
使用貸借とは、無償でモノを貸し借りする契約のことです。たとえば、以下のようなケースが該当します。
【例】
- 友人からタダで傘を借りた
- 親の車を無料で借りた
- 親から無料で土地を借りて家を建てた
- 弟が無償で兄の家に居候している…など
使用貸借の場合、モノの貸し借りをするうえで、賃料などの対価の支払いがありません。また、契約書の作成は必須ではなく、口約束のみで成立します。
賃貸借との違いは、賃料の支払いがあるかないかです。たとえば、子どもが親から土地を借りているケースでは、無料で借りていると「使用貸借」、親に地代や権利金を支払った場合は「賃貸借」となります。
共有不動産にも使用貸借はある
共有不動産に共有者が住んでいる場合であっても、使用貸借契約は存在しています。ここでは、兄弟間の場合と、第三者との場合の例を紹介します。
【ケース1】親が亡くなり、兄と弟が1/2ずつ実家を相続したが、その実家を兄が自宅として占有している
- 弟は、兄に対して共有持分割合(1/2)に応じた家賃相当額を請求できる
- 家賃を請求し、受け取っている場合は「賃貸借」
- 家賃請求をしていない場合は「使用貸借」が成立するとみなされる
【ケース2】親が亡くなり、兄と弟が実家を相続したが、弟が友人Cに無償で実家を貸している
- 兄は友人Cに対して持分割合に応じた家賃相当額を請求できる
- 兄が友人Cから家賃を請求すると「賃貸借」
- 賃料の請求をしない場合は「使用貸借」が成立するとみなされる
このように共有者間でも、使用貸借や賃貸借の関係になるケースがあります。
共有不動産での使用貸借の成立要件
共有不動産において使用貸借を成立させるには、共有者の同意が必要となります。また、「貸借期限」によっても要件は異なってきます。
短期間の使用賃借|持分割合の過半数の同意で成立
建物なら3年以内、土地であれば5年以内の貸借期限が「短期間」に該当します。短期間での使用貸借は、持分割合の過半数の同意があると成立します。
ここでいう「過半数」とは共有者の人数ではなく、持分割合の多さです。つまり、共有者のなかで持分割合の2/3をもっている人や、持分割合1/3の共有者が2人同意をすると、使用貸借は成立します。
長期間の使用賃借|共有者全員の同意で成立
建物なら3年以上、土地であれば5年以上の貸借期限は「長期間」に該当します。また、期間の定めがないケースも、客観的に見て長期の使用が想定される場合には、長期間とみなされます。
長期間の使用貸借を成立させる場合は、共有者全員の同意が必要です。共有者のうち、誰か1人でも反対している人がいる場合には成立しません。
共有不動産での使用貸借の解除要件
共有持分の使用貸借は、貸主や他の共有者にとってメリットはなく「解除したい」と思う人も少なくありません。どのような条件を満たすと解除になるのかまとめました。
持分割合の過半数の同意がある
持分割合の過半数の同意を得て、借主に解除の通知を行うと、使用貸借契約は終了します。契約終了後は、借主に対して賃貸借契約への切り替えや、不動産の明け渡しなどの請求もできます。
ただし、使用貸借をした際に、借主との間で「期間や目的を取り決めている」場合は、解除できないケースもあるため注意が必要です。
借主が死亡した場合も基本的に解除される
使用貸借は、借主が死亡した時点で原則として契約終了となります。契約が終了するため、借主の相続人に契約が引き継がれることはありません。したがって、貸主が退去の請求をすれば、借主の相続人は立ち退きに応じると考えられます。
ただし、使用貸借の契約時に特約を結んでいる場合は、例外で使用貸借が存続するケースも。また、貸主が引き継ぎを了承した場合にも、借主の相続人に使用貸借が引き継がれます。
共有不動産の使用貸借を放置するリスク
「今のところ何の問題もないから」「話し合いは面倒くさいから」といった理由から、使用貸借の状態のまま放置している人もいるかもしれませんが、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 維持費(税金・修繕費など)がかさむ
- 時効取得を主張される可能性がある
リスクがあることを踏まえ、長期間放置せずになるべく早く対処しましょう。
維持費(税金・修繕費など)がかさむ
共有持分をもっている場合、たとえその不動産に住んでいなくても、あるいは使っていなくても、維持費を負担しなければなりません。
維持費には、固定資産税や修繕費などがあり、大きな金額を要する場合もあります。一方で、使用貸借は「無償での貸し借り」の状態であり、借主に負担はありません。
貸主にとってメリットはなく、費用だけがかさんでしまうため、借主とよほど仲が良い場合や納得している場合以外は、賃貸借契約に切り替えましょう。
使用貸借している共有不動産の賃料を取ることは難しい
「使用貸借している借主から賃料を取りたい」と思う人もいるかもしれませんが、請求が認められにくい側面があります。使用貸借に対する賃料の請求は、裁判官によって「不当利得に該当するかどうか」で判断されます。
不当利得だと認められれば賃料の請求ができますが、長期間放置していた場合などは、不当利得に認められず、請求は困難です。長期間の放置は、「黙認していた」「許していた」として使用貸借が成立し、不当利得に該当しないと判断されるためです。
時効取得を主張される可能性がある
使用貸借の状態であっても、10年、あるいは20年間その不動産を占有している場合、不動産を借主の所有物にされる可能性があります。
たとえば、借主が死亡したあと、子どもがそのまま不動産を引き継いでおり、子どもは「自分の家だと思っていた(親から相続した)」といったケースです。
このように、一定の条件を満たすと不動産の所有権が占有者に移行することを時効取得と呼び、時効取得が成立すると、不動産は借主の所有物になってしまう可能性があります。
共有不動産のトラブル対処法
共有不動産に関するトラブルを解消するには、共有状態をなくすのが得策です。以下の方法を検討してみましょう。
- 共有物分割請求にて共有名義を解消する
- 共有持分を売却する
共有物分割請求にて共有名義を解消する
共有物分割請求とは、共有持分を持つ人が他の共有者に対して、共有状態の解消を求める手続きのことです。借主に自分の共有持分を買い取ってもらったり、不動産を売却して現金に換え、分割したりできます。
借主に対して、明け渡しや賃料の請求をするのは難しい傾向があるため、いっそ共有名義を解消したほうが、早い解決が見込めるでしょう。
共有持分を売却する
自分の共有持分を売却するのも、ひとつの方法です。共有不動産全体を売却したい場合は、他の共有者の同意が必要になりますが、共有持分のみであれば、自分で自由に売却できます。
共有持分を売却すると、まとまったお金を受け取れるため、これまでの費用負担の補填にも充てられるでしょう。共有持分を売却する際は、専門の買取り業者に相談するのがおすすめです。
まとめ
使用貸借は、貸主にとっては不利ともいえる契約状態です。とくに費用面の損失は、契約が長くなればなるほど大きな負担となっていきます。そのため、不動産を使用する予定がなければ早めに共有持分を売却して、不動産にかかる費用をなくすことをおすすめします。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。