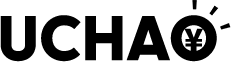公開日: |更新日:
相続登記の期限はあるの?
2022年6月時点で、相続した不動産の相続登記の期限に関する法的義務は定められていません。しかし相続登記の義務化に関する法案は公布されており、2024年4月からの義務化が想定されています。このページでは、相続登記の義務化に関して紹介しているので参考にしてみてください。
相続登記の期限はない
相続登記の期限に関する法的義務の有無
相続登記に関する法的義務は2022年6月時点で存在せず、期限も明確に定められていません。そのため、すでに相続した不動産の相続登記を後回しにしていても、法的義務がないため問題とならないケースが多いでしょう。
しかし相続登記の義務化に関して、適正な登記をされずに放置されている物件が全国的に問題化しています。例えば高速道路で用地買収するケースです。相続登記がされておらず所有者が不明な土地は、公共事業や災害対策の障害になる可能性も。また所有者を特定するのに多大なコストがかかるため、この現状を改善するべく2021年4月に不動産登記法の法案が公布されました。
そしてこの改正により、2024年4月から相続登記の義務化や、3年以内の手続き完了といった期限が設定される予定です。
義務化前の相続も対象となる
相続登記の義務化前に相続していた
不動産も対象
通常、法律の世界では「法の不遡及(ふそきゅう)」という概念があり、成立した法律によって成立前の行為や結果について裁いたり罰したりすることはできません。
しかし改正された不動産登記法によると、法的に相続登記の義務化が実行される前から所有していた不動産に関して、相続登記の法的義務が発生するようです。
相続登記の期限は指定日から3年以内
相続登記の義務化を考える上で、相続登記を行うべき期間は下記のように定められています。
- 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日
- 民法および不動産登記法の改正法の施行日
- 以上のいずれか遅い日から3年以内
つまり、相続登記の義務化が施行される前に所有していた相続不動産に関しても、新制度がスタートする日から3年以内に手続きが必要です。
また複数人で相続した物件や、複数世代にわたって未登記が続いている物件の場合、権利関係が複雑になります。相続登記の完了までに時間が必要になると考えられるため、顔を見たことの無い遠い親戚と揉めずに済むように、速やかに手続きを始めるのが大切です。
義務化後は過料の対象となる
10万円以下の過料
相続登記を期限以内に完了しなかった場合、罰則として「10万円の過料」が定められているため、早い段階から相続登記について考えるのが肝要です。もし期限までに間に合わない場合は、相続人申告登記を申請をするのが良いでしょう。
相続人申告登記とは「自分が相続人です」と法務局に申請し、登記簿上の所有者が亡くなっていることだけを公示する簡易的な登記です。正式な相続登記より負担が軽い手続きなため、何らかの事情によりすぐに相続登記ができない場合には、相続人申告制度の利用を検討しましょう。
まとめ
相続した不動産を登記する相続登記。2022年6月時点で義務化されていないものの、2021年4月時点で義務化について法案が可決されており、早ければ2024年4月から始まります。
先の話にも思えますが、複数人で相続した物件や複数世代にわたって未登記が続いているなど、状況によって問題が複雑化することも。当事者だけで手続きが難しい場合は、専門家へ相談してみましょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。