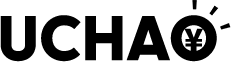公開日: |更新日:
私道の共有持分(私道持分)も相続財産に含まれる?
このページでは、私道の共有持分(私道持分)の相続について解説しています。相続財産でありながら見落とされがちな私道持分に関して正しく理解し、遺産分割協議におけるトラブルなどを回避しましょう。
私道の共有持分も相続財産
そもそも「私道」とは地方自治体などの公共団体でなく、個人や民間企業などが私的に所有している道路の総称です。また、私道について個人が単独で所有しているのでなく、複数の人物や複数の世帯で共有している場合、それぞれに共有持分(私道持分)が発生します。
複数世帯の私道を共有して公衆用道路扱いにしている場合
例えば自宅や土地は被相続人の所有物であったとしても、自宅前の私道については複数の世帯で共有しており、被相続人は私道持分のみを所有していたというケースがあります。
その際、個人だけで私道を使っているわけでなく実質的に公道のような公衆用道路として扱われている場合は、所有者自身が私道持分を所有している事実を忘れてしまうケースも意外と多いのです。
私道の共有持分(私道持分)も通常の不動産と同様に相続財産に含まれます。そのため、私道持分を所有している人が亡くなった場合、相続人は遺産分割協議において私道持分についても相談し、取り扱い方を考えておかなければなりません。
私道持分が相続財産から漏れやすい理由
固定資産税が非課税である場合
私道部分が公衆用道路として認められている場合、私道に関して固定資産税が非課税となります。
固定資産税が非課税になることで納税通知のような所有していることがわかる連絡がありません。結果として所有している事実を忘れてしまいがちです。
個人の所有物としての意識がない
根本的に「道路」は公共物であり、個人が所有・共有しているという意識が一般的でない場合もあります。そのため、被相続人が亡くなった際に相続財産を確認しようとしても、私道や私道持分についてはチェック対象から漏れることが少なくありません。
資産価値としての評価が低い
私道は相続財産として認められる一方、私道の価値は無評価であったり宅地の3割程度まで下げられたりと、資産価値が少なくなっています。
不動産としての財産価値が少ないことから、そもそも相続時に議論の対象として注目されることがなく、いつの間にか相続財産として忘れられてしまうといったことが起こります。また、特に共有持分として私道を共有している場合、さらに資産価値が分割されてしまうため、相続財産のリストから漏れやすくなってしまうことも考えられるでしょう。
私道の共有持分の登記を漏らしたら
私道や私道持分も通常の不動産のように相続財産としての扱いを受ける以上、私道を相続した際にも当然ながら相続登記が必要です。そのため、相続財産に私道や私道持分が存在している場合、相続人は相続後に不動産登記を行って所有者の変更を公的に手続きしておかなければなりません。
私道持分の登記が完了していないと自宅の再建築を行えない場合もあるため、もしも私道持分の登記漏れに気づいた場合、速やかに司法書士へ連絡して相続登記を完了させることが必要です。
私道持分の遺産分割協議方法・流れ
ここでは私道持分が相続財産として含まれていた場合に、どのような流れで相続人は遺産分割協議を進めれば良いのか、順序立てて解説していきます。
1回目の遺産分割協議で私道持分を含めて行うことができた場合
1.相続人の確定
私道持分であっても通常の不動産相続と同様に、まずは遺産分割協議の前に全ての相続人を確定しなければなりません。遺産分割協議は相続人全員の同意にもとづいて完了するため、最初に相続人を正しく確定しておかなければ後になって遺産分割協議をやり直さなければならなくなるため注意が必要です。
なお、相続人としては法定相続人だけでなく、被相続人の遺言によって指定されている人物がいないかなども詳しく確認しておきましょう。
2.相続財産の確定・財産目録の作成
私道持分を含めて、どのような相続財産があるのか確定し、全ての財産について網羅した財産目録を作成します。
相続財産として遺産分割協議の対象になる財産が漏れていた場合、その財産的価値によっては遺産分割協議そのものを最初からやり直さなければならない可能性もあるため、相続人の確定と相続財産の確定は慎重に行うようにしてください。
3.遺産分割協議書の作成・署名・押印
相続人が互いに話し合うなどして、私道持分を含めた相続財産について分配方法や相続する内容を決定します。相続の方法が確定すれば、遺産分割協議の内容を改めて「遺産分割協議書」としてまとめ、原則として相続人の全員が遺産分割協議書へ署名・押印します。
なお、遺産分割協議そのものに関しては、相続人の全員が一堂に会して行う必要はありません。重要な点は全員が話し合いの内容に理解し、納得した上で署名・押印をするという点です。
借金などマイナスの遺産がある場合も他の相続財産と同様に扱います。
私道持分が相続財産から漏れたために再度遺産分割協議を行う場合
私道持分が相続財産から漏れていたと発覚した場合、改めて遺産分割協議を行わなければなりません。なお、私道持分の財産的価値が低い場合、すでに話し合いが済んでいる財産については触れず、漏れていた私道持分についてのみ再度遺産分割協議を行うだけで良い場合があります。
1.相続人の再確定
私道持分の存在が最初の遺産分割協議のすぐ後に発覚した場合、相続人に変更はないかも知れません。しかし私道持分の存在が発覚するまで時間がかかった場合、相続人の構成が変化している可能性もあります。
相続人が死亡している場合や認知症などによって遺産分割協議へ参加できない場合、相続権を引き継いだ人が代襲相続人として遺産分割協議に参加するといった対応が必要になることもあるでしょう。
2.遺産分割協議書の作成・署名・押印
一般的に私道はそれが面している自宅や不動産とセットで扱われる上、資産価値が高くないため、相続する人も通常はそれらの不動産を相続した人になります。ただし、その他の相続人が納得しない場合、改めて合意を得られるまで遺産分割協議が再開されます。
遺産分割協議の内容がまとまれば、再び遺産分割協議書を作成して全ての相続人が署名・押印するといった流れです。
3.遺産分割協議に協力が得られない場合の手続
遺産分割協議の再協議で非協力的な相続人がいた場合、家庭裁判所へ遺産分割調停や審判を申し立てることもあります。
なお、私道そのものは価値が低くとも、宅地として道路に面した不動産を活用するためには不可欠なものであり、協議に参加するメリットのない相続人に対して代償金を支払わなければならないケースもあります。
まとめ
私道の共有持分(私道持分)は立派な相続財産ですが、相続財産から漏れやすく、遺産分割協議で話し合われないまま問題として残る可能性もあります。
しかし、私道は自宅など道路に面した不動産を活用する上で重要な価値を持つため、相続財産に私道持分が含まれていたり、後から相続財産に私道持分が含まれていたと発覚したりした場合は、不動産相続や共有持分の取り扱いに詳しい専門家へ相談してスムーズな解決を目指すようにしてください。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。