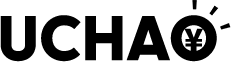公開日: |更新日:
2024年に義務化される相続登記とその背景とは?
相続した不動産について、従来は相続人が登記しなくても罰則などがありませんでしたが、2024年からは相続人による相続登記が義務化され、違反すれば罰則金などのペナルティも科せられることとなります。
このページでは、相続登記の義務化で変化するポイントや、義務化の背景などをまとめて解説していますので、いざとなってから慌てないように準備しておきましょう。
相続登記の義務化について
相続登記の義務化とは?
これまでは相続で土地を取得したとしても、その土地について名義人を相続人のものへ変更したくなければ、そのまま放置することが可能でした。しかし、2021年に相続登記の義務化に関する改正法案が可決され、2024年を目処として施行されることとなりました。
そのため、制度施行後は相続によって不動産を取得した全ての人が、一定期間内に相続登記を完了しなければならなくなり、もしも相続登記をせずに放置していれば「10万円以下の過料」を支払わなければなりません。
義務化で変化する相続登記のルール
相続登記の義務化で重要な変更点は以下の4点です。
- 相続登記の義務化と相続登記を完了するまでの期限について
- 所有者の住所や氏名に変更があった場合の変更登記について
- 法務局による所有者情報取得の仕組み
- 土地の国庫帰属制度(所有権の放棄制度)
相続登記の期限
相続登記の義務化を定めた改正法が施行されるまで、相続登記そのものに「いつまでに手続きを完了しなければならない」といった期限は存在しません。
しかし相続登記の義務化がスタートした後は、相続を知った日から3年以内に相続登記を定めることが必要と定められています。
なお、3年以内という期間には、同時に「正当な理由なく」といった条件が付けられていることも重要です。つまり、ただの怠慢などで相続登記の期間を超えてしまった場合、10万円の罰金が科せられるかも知れませんが、何らかのやむを得ない事情があったと認められれば、罰則を回避することも可能です。
また、相続人が遺産分割協議などで不動産を相続した場合だけでなく、例えば被相続人が生前に作成した遺言書によって相続人が決められるような場合でも、やはり同様に「3年以内の名義変更」が求められています。
所有者の変更登記の期限
不動産相続などにおいて、相続税などの期限があるため、ひとまず仮として不動産の相続割合を決定して相続登記を行い、さらに落ち着いて遺産分割協議を行った結果、改めて不動産の分配割合が変更されるといった事例も考えられます。このような場合でも、原則として相続登記の期間と同様に変更登記の期限が定められており、「3年以内」の名義変更を完了しなければなりません。
なお、期限を過ぎて相続登記が完了されなかった場合、10万円以下の罰金といった罰則が定められていることも重要です。
その他、所有者が引っ越して現住所が代わったような場合、変更から「2年以内」に正当な理由なく手続きを怠ると「5万円以下」の過料の対象となります。
改正前に所有していた不動産や、住所変更の登記などが完了していない不動産についても、これらの期限や罰則は適用されます。
法務局による所有者情報取得
不動産の所有者について、法務局が生年月日などの個人情報を取得できるようになります。
土地の国庫帰属制度(所有権の放棄制度)
相続した土地を取得したくない場合、土地の所有権を放棄して国庫へ帰属できる制度が始まります。
義務化に伴う登記手続きが一部簡略化される
これまでの相続登記に関するルールでは、例えば被相続人の遺言で相続財産を受ける場合、相続登記の手続きに法定相続人全員もしくは遺言執行者の協力が不可欠でした。
言い換えれば、1人でも非協力的な相続人がいた場合、あらかじめ定められている期間内に相続登記を完了できない可能性も考えられます。
そこで法改正後は、遺言書によって不動産を遺贈された相続人は、本人だけで相続登記を実行できるようになりました。
また、後々の遺産分割協議によって不動産の取り分が変更されたという場合であっても、不動産を取得した人が故人で相続手続きを行えるようになりました。
相続人申告登記(仮称)が設けられる
原則として、相続開始から3年以内に相続登記を完了しなければなりません。しかし正当な事情によって遺産分割協議が長引くなどして3年以内の相続登記が困難になった場合、相続人が自分を相続人として法務局へ申告し、相続登記の義務を一時的に会議できます。
また、相続登記は完了しておらずとも、不動産を実質的に引き受ける相続人が住所・氏名を法務局へ提出することで、少なくとも所有者不明の不動産を生じさせるリスクは低減可能です。
なお、正当な事情や、やむを得ない事情によって相続登記が期限内に終わりそうにないと判断すれば、その事実を法務省へ伝えて罰則を免除してもらえる可能性があります。
実際にどのような状態であれば「やむを得ない事情」として認定されるのか、その判断基準は法務省にあってケースバイケースという点は否めません。ただし、2022年7月時点では具体的な基準が定められていないものの、今後は法改正の施行に合わせて明文化されると想定されています。
相続した土地を登記したくない人のための「国庫帰属制度」
相続によって土地を取得することになっても、まるで使い道がなく売却も困難な土地は相続人にとって固定資産税など負担となるばかりで、メリットを感じられないケースも少なくありません。しかし、現行法では土地が要らないからといって、相続財産から土地だけを選択的に放棄することはできませんでした。
相続登記の義務化に伴い、各地の法務局へ申請して法務大臣の承認を得ることで、土地の所有権を放棄して国庫へ帰属させることができるようになります。
ただし、所有権放棄が認められる土地にも条件があります。
例えば土地の上に建物が建っていたり、抵当権などが設定されていたりする土地は放棄できません。また、有害物質で汚染されている土地や、所有権や範囲などに関して係争状態にある土地も対象外です。
その他、土地を国庫へ帰属させる際は「管理費(10年分)」として費用がかかるともいわれており、実際の運用に向けた動向をチェックしておきましょう。
相続登記義務化の背景とは?
所有者不明の土地の増加
所有者の死後、相続人による不動産の相続登記が適正に行われなければ、その土地などの現在の所有者について行政が把握できません。
そしてそのような「所有者不明土地」は日本全国でおよそ2割に及ぶとされており、個人が活用することも行政が公共用地として買い取ることもできず、社会的に大きな問題となっています。
そのため国は相続登記の義務化によって所有者不明土地の問題を解決し、合理的に土地活用を進めていける体制を整えることに決めました。
所有者不明土地が増えればどうして問題なのか?
所有者が不明な土地ということは、例えばその土地が雑草などで荒れ果ててしまったり、不法投棄の現場になっていたりしても、管理して問題を是正する人がいないということです。そのため地域環境が悪化したり、犯罪が放置されてしまったりといった問題があります。
また、公共用地として行政が買い取れないため、例えば災害対策工事を実施することもできず、地域の安心安全な環境を脅かすリスクになっていることもあるでしょう。
超少子高齢化が進む日本社会において、今後はますます所有者の死亡による所有者不明土地の増加が懸念されており、早急な解決策が必要とされていました。
相続登記をしなかった際に起こるリスク
相続登記が義務化されたとして、その後も相続登記を行わずに放置してしまった場合、どのような問題やデメリットが発生するのでしょうか。ここでは相続登記をしなかった際に考えられるリスクについて解説していますので、問題点をしっかりと把握した上で対処していきましょう。
不動産に関する権利関係が複雑化してしまう
相続登記を適正に完了していなければ、誰がその不動産の正式な所有者であるのか公的に示すことができません。また、もしも不動産を引き継いだ相続人が相続登記をせずにそのまま亡くなってしまった場合、権利関係が複雑化してしまい、改めて相続登記を行おうとした際に色々と問題が生じてしまう可能性もあります。
加えて、単独所有でなく不動産を複数の相続人で共有した場合、さらに権利関係が複雑化しやすくなるので、必ず共有登記を完了して現時点での権利関係を明確化しておくことが大切です。
義務化されたから相続登記を行うのでなく、後々のリスクやトラブルを避けるために相続登記を速やかに完了するようにしましょう。
不動産の売却をスムーズに進められない
相続登記が行われていなければ、自分が不動産を相続した人間であり、現在の正しい所有者であると明示できません。そのため、不動産の売却を進めようとしても、所有者として証明できないので取引がスムーズに進められない可能性が高まります。あるいは、そもそも相続登記を完了してからでないと不動産の売却を行えないので、相続登記に時間がかかってしまえば不動産の売り時を逃したり、不動産の評価額が下がってしまったりといったリスクもあり得ます。
共有持分の相続であった場合、さらに事情が複雑化することを避けられません。相続が発生した時点で適切な話し合いを終えておき、速やかに相続登記を行っていなければ、改めて相続登記を共有名義で行おうとした時点で相続人の一部が亡くなっており、相続権がさらに別の人物へ引き継がれている場合もあります。そうなると、場合によっては共有そのものについて話し合いが初期化されてしまうこともあるでしょう。
身に覚えのない理由で不動産を差し押さえられるリスク
共有者の中に借金を抱えている人がいた場合、他の共有者が気づかない間に不動産が第三者から差し押さえられてしまうといったリスクがあります。
債権者が差し押さえられるのは債務者が保有していた共有持分のみであり、債権者だからといって不動産の全てを差し押さえることはできません。しかし差し押さえ分がある時点で不動産を自由に取り扱えなくなるため、実質的に負担を押しつけられることになります。
相続登記の義務化に合わせて意識すべき具体的な登記方法
相続登記が義務化されれば、実務的にも法的にも期間内に相続登記を完了しなければなりません。ここでは、相続登記の義務を果たすために必要な方法や具体的なポイントを解説しています。相続登記義務が発生した際に混乱しないよう、あらかじめチェックしておいてください。
3年以内に相続人全員の共有登記をする
相続登記は相続が発生した時点、あるいは自分が相続不動産について所有者になると知った時点から3年以内に行わなければなりません。単独所有でなく共有であった場合、当然ながらそのルールは共有者全員へ反映されます。つまり、相続が発生した時点から3年以内に全ての相続人が同意した上で遺産分割協議を完了し、そこで決められた共有持分に従って相続人全員が共有登記を済ませることが必要となります。
実際問題、3年以内に相続人の全員がきちんと話し合いを行って相互理解を叶え、その上で遺産分割協議をまとめて共有名義の相続登記を済ませれば、それが最もリスクやその後のコスト、デメリットを回避する最善策と考えられるでしょう。
一方、もしも相続登記を進められなかった場合、「相続人申告登記」を検討することになります。
法務局で「相続人申告登記」をしておく
世の中には様々な事情があり、家族ごとに多様な関係が存在します。そのため、例えば不動産の所有者が亡くなって相続が発生し、自分が不動産を相続する該当人物の1人であると知ったとしても、速やかに遺産分割協議へ進んだり共有持分を決定したりできるとは限りません。特に相続人が複数いる場合は話し合いの難易度も高まっていきます。
そのような場合、まずは自分だけでも「相続人申告登記」を行っておくことが大切です。
相続人申告登記は法務局で行いますが、仮に遺産分割協議が完了していなくても、相続人申告登記を行っておけばひとまず相続人として相続登記申請義務を果たしたものと見なされます。
相続放棄について
相続放棄とは、相続人として被相続人の遺産を受け継ぐ権利を放棄するという宣言です。
相続放棄を行えばそもそも相続人としての権利を失うため、不動産の名義人として相続登記を行う必要もありません。
ただし、相続放棄をすれば不動産だけでなく全ての遺産について相続することができなくなり、さらに相続放棄には期限があることも重要です。
相続放棄は相続人になったと知った時点から原則3ヶ月以内に行います。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。