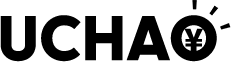公開日: |更新日:
兄弟間で不動産を分ける方法のルール
相続の発生により1つの不動産を兄弟間で分けるというシーンは決して珍しいものではありません。また、土地のみの相続のほか、土地と建物を相続するケースもあるでしょう。
今回は、兄弟間で不動産を分けるいくつかのパターン事例とともに、どのように分けるのかを解説していきます。
不動産相続のパターン
不動産の相続は、対象となる不動産によって様々なケースが考えられます。もちろん、不動産を相続する場合に、相続人同士で共有とせず単独所有とすることもあります。
まずは、兄弟で共有とする2つのケースを紹介しましょう。
土地のみを兄弟で共有するケース
相続対象となる不動産が土地のみのケースは、比較的単純といえます。
例えば、相続対象である土地が1,000㎡だったとします。これを兄弟2人の共有とした場合、法定相続分では2分の1ずつ取得することとなります。もし、この土地が整形地であれば分筆することもでき、500㎡ずつにそれぞれの単独所有とすることも可能といえるでしょう。このように、土地のみを比較的少人数で相続するのであれば、共有状態を続けるほか、分筆や売却など様々な方法での運用・処分を選ぶことができる点も特徴です。
土地建物を兄弟で共有するケース
不動産を相続する場合の大半が土地・建物の両方を相続するケースでしょう。土地と建物を兄弟で共有するケースでは、土地では可能となる分筆ができないということもポイントの一つです。土地建物を法定相続分に則って兄弟2人で相続した場合、土地を2分の1ずつ、建物においても2分の1ずつの共有となります。建物は分割できない不動産ですから、今後売却を検討する場合も兄弟2人が同意する必要があり、賃貸として運用する場合でも勝手に第三者へ貸すことはできません。こういったケースでは、代償分割などを可能とするため、遺産分割協議を行うことも先々のトラブルを防ぐ方法といえます。
相続の基本【法定相続分】
先程少し出てきた『法定相続分』は、相続において基本ともいえるものですので、簡単に説明していきましょう。
『法定相続分』とは、民法第900条に下記のように定められています。
- 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
この条文に倣って考えると、被相続人が親であり、相続人が子どもである兄弟2人のみである場合、各2分の1を相続するということとなります。また、配偶者がいる場合は配偶者が2分の1を相続するため、子どもたちは残りの2分の1を兄弟で分け4分の1ずつを相続します。
このように相続のルールが民法で定められていることも覚えておきましょう。
相続時の話し合い【遺産分割】
『法定相続分』が民法で定められた相続ルールとお伝えしましたが、『遺産分割』についても相続時に欠かせないポイントです。
民法第三節の遺産の分割には、第906条では【遺産の分割の基準】が下記のように定められています。
- 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
これを基準とし、相続では遺産分割協議を行うことを認めています。
『遺産分割協議』とは、相続人の全員で誰がどの財産を相続するかを話し合うことをいい、民法第907条【遺産の分割の協議又は審判等】により、ルールが定められているのでチェックしましょう。
民法では、遺産分割協議は“いつでも”自由にすることができるとされています。遺産分割協議は、法定相続分での相続をしない場合や被相続人が遺言書を残していない場合などに行われます。
遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあり、それぞれどのような方法なのか、メリット・デメリットもあわせて確認してみましょう。
現物分割
現物分割とは、財産をそのままのかたちで相続人がそれぞれ取得することをいいます。例えば、土地・建物・預貯金など金額にかかわらず相続人間で分割する流れとなります。2,000万円の土地と建物は長男、1,000万円の預貯金を次男が相続するといったことも可能な点が特徴です。
現物分割は、残された遺産をそのままの状態で分け合うことになるため、わかりやすさがメリットといえるでしょう。ただし、相続する財産の価額はバラバラであることが多く、均等に分割できない点がデメリットでもあります。
代償分割
代償分割とは、他の相続人に比べて多くの財産を相続した者がその代償として現金を支払う方法をいいます。これは、遺産が不動産のみの場合などで現物分割が不可能な際の方法でもあります。もちろん、こういったケースでも他の相続人が代償は不要との同意があれば無償とすることもできます。ただし、税金対策として代償することが一般的でしょう。
代償分割は、不動産などを共有持分ではなく単独で取得することができ、尚且つ他の相続人も公平に財産を取得できる点がメリットでしょう。デメリットを挙げるとすれば、他の相続人に支払う現金を準備する必要がある点です。資金を用意できない場合は、結果的に不動産売却を検討しなくてはなりません。
換価分割
換価分割は、相続する不動産を売却して相続人に均等に分ける方法をいいます。相続不動産に居住する者もおらず、管理も難しいのであれば換価分割の方法がおすすめかもしれません。また、現物分割や代償分割での協議が調わないケースでも用いられる方法です。
不動産の売却益を相続人同士で分け合うため、全員が納得して相続することができる点もメリットでしょう。換価分割の場合は、不動産が2,000万円で売却すると兄と弟が1,000万円ずつ取得することが可能です。
換価分割では、不動産売却に伴い譲渡所得税の対象になる点には注意しましょう。
相続人全員が納得できる方法を!
不動産の相続には、法定相続分で分割する方法のほかにもいくつかの方法があることを紹介しました。
兄弟での相続のように相続人が複数いるケースが大半のため、どのように相続するかは相続人全員で話し合いを行い決める必要があります。協議が面倒だからと共有持分での相続を決定するのではなく、“将来的に相続した不動産をどうしていきたいか”をしっかりと考え、相続人全員が納得のいく方法を選択しましょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。