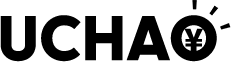公開日: |更新日:
相続登記を放置しても大丈夫?
相続登記を行わず、不動産などの手続きをそのまま放置していると、どのような問題が生じるのでしょうか。このページでは、相続登記を放置した場合のリスクや、2024年からの相続登記の義務化にもとづいたルールの変更点などをまとめて解説しています。
相続登記の放置は問題になる?
法的義務がない間は罰則などはない
相続登記を行わず放置しておくことで、想定されるリスクやトラブルといったデメリットは少なくありません。しかし、2022年7月現在において相続登記は法的義務として明文化されておらず、仮に相続登記を行わずに放置していても罰則などの問題が発生することもありません。
そのため、新たな相続問題や不動産の売却といった事態が発生しない限り、一般論としては相続登記を放置していても即座に問題となることはないといえるでしょう。
2024年の義務化の後で放置は問題
法改正によって相続登記が義務化され、その開始は現時点で2024年と想定されています。
相続登記が義務化された後で放置していると、場合によっては10万円以下の罰金が科せられるといった問題が発生します。
そのため、相続登記の義務化後は必ず期限内に相続登記を完了させることが必要です。なお、相続登記の期限は、相続から3年以内に申請すべきと定められていることもポイントです。
義務化の前でも相続登記はしておくべき
相続登記を行う上で最もデメリットとして挙げられやすい内容の1つが、司法書士へ依頼する費用でしょう。
また、相続登記を手続きしようとすれば関連資料を全てそろえなければならず、事務的な手間がかかります。
しかし、相続登記は司法書士へ依頼せずとも本人で行うことが可能であり、そもそも相続登記を行わず放置することで想定されるリスクは少なくありません。
メリットとデメリット、リスクとベネフィットのバランスを考えると、相続登記が義務化される前であっても、不動産を相続してから「10ヶ月以内」に相続登記を行っておくことが無難と考えられそうです。
相続登記を放置することで生じる罰金以外の問題
相続登記を放置した場合、義務化後の罰金の他にも様々な問題が懸念されます。
相続問題が複雑化して話し合いも困難になる
相続登記を放置したまま相続人が死亡すれば、その配偶者や子供など次の相続人へ不動産の所有権が移ることになります。また、世代を経るごとに相続人の数が増えていくこともあるでしょう。しかし、不動産の名義は已然として祖父母の世代のものとなっており、改めて遺産分割協議によって不動産の所有者を誰にするか決めなければなりません。
ところが、祖父母との関係が薄れていたり、遺産分割協議に参加する人数が増えていたりした場合、協議は難航し問題が複雑化していく恐れが生じます。
相続人の病気や事故で遺産分割協議が困難になる
現在は健康な人であっても、いつ病気を患ったり事故に遭ったりするか分かりません。また、中高年層では認知症といったリスクも現実味を帯びてきます。
相続した時には相続人の全員が健康であっても、放置して年数が経つことで、いざ改めて相続登記を行おうとした時には認知症が進んで話し合いが困難になるかも知れません。
遺産分割協議に参加すべき相続人が音信不通になる
世代交代や病気・事故などによって相続人の一部へ連絡できなくなれば、遺産分割協議もスムーズに進めることができなくなります。
どうしても相続人が見つからない場合、「不在者財産管理人」を選任する必要がありますが、成年後見人と同様に手続き完了まで時間や費用がかかります。
公的な書類が消滅してしまう恐れ
相続登記には、被相続人の戸籍や住民票の除籍の附票・除票、改製原戸籍の附票といった書類が必要です。
ただし、戸籍を除いて住民票の除票や除籍の附票、改製原戸籍の附票といった書類は保管期間が5年と定められており、それを過ぎれば自治体によっては関連資料が破棄されるといったケースもあります。
必要書類が消滅してしまえば、そもそも相続登記をスムーズに進めることができません。
他の相続人が勝手に相続登記を行って不動産を売却する恐れ
複数の相続人がいる場合、例えば長男が自宅として不動産を相続し、他の相続人は不動産に代わる現金などを多めに受け取るといった合意が得られることもあるでしょう。
しかし、遺産分割協議において不動産の分け方が決められていたとしても、相続登記などが完了していない場合、他の相続人は法的に認められた自分の相続分について先に登記できることが重要です。
これにより、例えば相続人が自分の借金の弁済として不動産の一部を売却した場合、残りの相続人などが自由に不動産を取り扱えなくなる恐れが拡大します。
遺産分割協議の内容と異なっていても、実際に相続登記が先んじて行われ、土地や家屋の一部が第三者のものになっていた場合、例えば本来の相続人である長男が自宅を改装したり売却したりしようとしても、第三者が同意しなければ計画を進められなくなります。
また、場合によっては不動産の所有権を長男へ譲渡するために、費用を請求してくるケースも考えられ、本来であれば支払う必要のないコストを強いられてしまいかねない事態は重要です。
初心者でも自分で相続登記はできるのか?
相続人が個人で相続登記の手続きを行えるのか。結論からいえば、可能です。
ただし、そのためには色々と準備しなければならないことがあり、手続きのための事務作業も増大します。
また、手続き内容に不備があれば手続きが完了しないばかりか、タイミングによっては罰金の対象にもなりかねないため、基本的には司法書士などのプロへ相談して、相続登記を進めていくことがトータルのコストメリットを考えた上でも大切です。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。