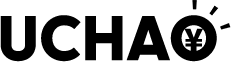公開日: |更新日:
共有名義不動産の取扱い方法を徹底調査!
このページでは、共有名義不動産の取扱いについて解説しています。
単独所有の不動産が相続により共有名義となる事例は多数あります。思わぬタイミングでの相続によって、親族間の共有物に至るケースは稀ではありません。そういった場合に、不動産をどのように取扱うかは大切なポイントといえるでしょう。
ここでは、不動産を運用または売却するために、どのような手続きや流れとなるのか合わせてお伝えしていきます。
共有名義不動産の建て替え・取り壊しは可能?
共有名義の不動産の取扱いとして挙げられるのが、『運用』と『売却』の2つです。
『運用』とは、不動産の建て替えを行い相続人が居住するケースのほか、賃貸住宅として第三者へ賃貸するケースなどが当てはまります。また、『売却』では、土地建物をそのままの状態で売却するケースや建物を取壊して土地のみを売却するケースなどがあります。
このように、共有不動産であっても、建て替えや取り壊しを含む、運用・売却を行うことは可能です。但し、これらは法律に則って行う必要があるため、どのようなルールで実施するのかについても覚えておくことが重要です。
では、共有不動産の建て替え・取り壊しの基本的なルールについて確認していきましょう。
共有名義不動産を建て替え・取り壊しのルール
共有不動産を建て替え、取り壊すことは、民法では“変更行為”に該当します。
変更行為は民法第251条にて『各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。』とされており、共有者全員の同意が必要となる行為になります。また、共有不動産である土地建物または取り壊したのち土地を売却する行為は“処分行為”となり、これについても民法251条にあたり、共有者全員の同意が必要です。
要するに、共有者が2人であろうと5人であろうと、その全員の同意がないと建て替えや取り壊し自体ができないということです。また、全員が同意した場合でも話し合っておくべきなのが、費用の負担についてでしょう。
さっそく、共有不動産の建て替え・取り壊しの費用について見ていきましょう。
費用の負担はどうなるの?
共有不動産の建て替え・取り壊しに伴う費用は、共有持分の割合に応じて負担するケースが多いことも特徴です。 共有名義不動産とは、同一の不動産を複数人で所有している状態にある不動産をいいます。各共有者は、同一の不動産に対して、それぞれ所有権を有しているということになり、この所有権の割合が“共有持分”です。例えば、親が所有していた不動産を兄弟2人が法定相続分に則って相続した場合、各自2分の1ずつの共有持分を有していることとなります。
そして、この共有持分に応じて費用負担すると考えると、建て替えまたは取り壊しにかかった費用総額を半分ずつ負担するというのが一般的です。
しかし、実際は共有名義不動産を建て替え・取り壊したのち、誰がどのように取扱うのかという点も費用負担を決めるポイントといえます。取り壊したのち、土地のみを売却するケースでは、取り壊し費用と売却によって得た収益の両方を共有持分に応じて決定してもトラブルの発生は少ないですが、共有者の一人が居住のために共有名義不動産を建て替えるケースではどうでしょうか。共有持分に応じて費用を負担し建て替えをしても、大きなメリットがない他の共有者に反対されてしまう可能性もあります。こういったケースでは、単に共有持分に応じた負担割合ではなく、共有者全員の話し合いにより決めることが大切です。
共有名義不動産の建て替え・取り壊しに伴うトラブル
ここからは、共有名義不動産の建て替え・取り壊しに伴うトラブル事例2つを紹介します。
共有者の同意を得られない
先に説明したとおり、共有名義不動産の建て替え・取り壊しは、共有者全員の同意のもとでなければ行うことができません。そのため、トラブルとして多いのが全員の同意を得られず、話が進まないといったケースです。建て替え・取り壊しには費用がかかり、まとまった資金がないため応じられないという場合もあります。
反対する理由が費用負担であれば、その共有者の持分を買い取ってしまうということも一つの方法でしょう。また、他の共有者すべての持分を買取り、不動産を単独所有する方法もあります。長期にわたり共有者間の協議が調わない場合は、何らか別の方法での対処が望ましいといえます。
費用負の担割合と持分割合の差は贈与とみなされる
建て替えを行った際に生じる事例の一つで、新築にかかる費用の負担割合が共有持分割合と異なる場合、その差額部分に贈与税がかかることがあります。例えば、兄弟が2分の1ずつ所有する不動産を3,000万円で建て替えるとしましょう。本来であれば持分に応じて1,500万円ずつ負担しますが、兄が2,000万円負担、弟が1,000万円の負担をしました。その場合、兄の負担割合が3分の2、弟の負担割合が3分の1となります。新築した建物の共有持分をこれまでと同様2分の1ずつ登記すると、弟は負担割合との差額500万円を兄から贈与されたものとみなされます。
持分割合と異なる費用負担をする場合は、建て替え後の持分変更または贈与税についても考えておきましょう。
共有名義不動産の話し合いは最初が肝心!
共有名義不動産の取扱いは、単独所有の不動産と比べて手続き等に手間がかかるのが特徴です。そのため、建て替えや取り壊し、売却など共有不動産を今後どのように利用または処分するのかは、早めに話し合うことがポイントといえるでしょう。
建物の建て替え・取り壊しの協議がまとまらない場合などは、そのままの状態で放置せず、自己の共有持分のみの売却を検討してもいいかもしれません。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。