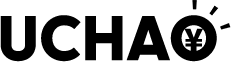公開日: |更新日:
相続登記における登録免許税の免税措置
相続登記を進めるにあたって、不動産の固定資産評価額と税率に応じた登録免許税が発生しますが、条件によっては免税措置が適用されて登録免許税の税率を下げられることがあります。このページでは、相続登記における登録免許税の免税措置について解説しています。
相続登記における免税措置のケースは主に2つ
相続登記において登録免許税の免税措置が適用されるケースとしては、大きく2つのパターンが考えられるという点が重要です。1つは不動産を相続した人が相続登記をしないで死亡した場合、もう1つは「不動産価額が100万円以下の土地」であった場合です。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
概要
例えば亡くなった祖父から父が土地を相続したとして、父が相続登記を行う前に死亡して、息子へ改めて土地が相続された場合、息子は自分がその土地の所有者であることを相続登記によって登録しなければなりません。
しかし、本来であれば祖父から父へ所有権移転登記が行われているべきだったものの、実際には父が生前に相続登記を行っておらず、そのままでは息子が「父から相続した土地」として相続登記を進めることができなくなります。
そこで、改めて祖父(故人)から父(故人)へ所有者名義を変更するための相続登記に関しては、登録免許税の免税措置が適用されて免税となります。
なお、息子の相続登記に関しては登録免許税が発生するため注意してください。
また、例えば父が生前に第三者へ土地を売却していたり、あるいは息子が相続放棄によって土地の相続権を放棄したりしたような場合であっても、祖父から父への相続(一次相続)の登記に関する登録免許税は免税となります。
免税される税率は?
本来であれば、対象となる土地の固定資産評価額に税率0.4%が乗算されて登録免許税の金額が決定されますが、免税措置が適用されれば税率はゼロとなり、当該登記に対する登録免許税のコストもまたゼロとなります。
免税措置はいつまでか?
土地を相続した個人が相続登記を行う前に死亡していた場合で、かつ平成30年4月1日から令和7年3月31日までの期間において受ける、当該個人を登記名義人とする登記については登録免許税が免税となります。
免税を受けるにはどうすればよいか?
登録免許税の免税措置の適用を受けたい場合、免税根拠となる法令条項を申請書に記載しなければなりません。
具体的には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という内容を申請書に記載します。
実際の記載場所や方法などは改めて窓口などでご確認ください。
土地の評価額が100万円以下の場合
概要
不動産相続によって所有権が移転される土地に関して、その不動産価額が「100万円以下」である場合、条件次第で登録免許税が免税となり費用負担が発生しません。
なお、平成30年度の税制改正によって定められた従来の登録免許税の免税措置の要件では、対象となる不動産の価額が「10万円以下」とされていましたが、令和4年度の税制改正に伴って現行の「100万円以下」となり、さらに対象が「全国の土地」へと拡充されていることも重要です。
土地の評価額が100万円以下の場合の免税措置に関しては、要件として大きく2つのものが定められており、そのどちらか一方へ該当する場合に免税措置が適用されます。
また、不動産を複数の相続人で共有する場合、当該不動産全体の価額へ共有持分の割合を乗算した金額が「不動産の価額」となる点も覚えておきましょう。これにより、土地そのものは100万円以上の価額であっても、共有持分の割合によって免税措置を受けられる可能性が残ります。
免税措置を受けるための2つの要件とは?
土地の不動産価額が「100万円以下」であるという条件の他に、免税を受けるための要件としては、以下の2つが挙げられます。
- 平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記
- 令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記
なお、「平成30年11月15日」の法的根拠は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日」となっています。
免税措置はいつまでか?
要件によって期間の始めに違いがあるものの、いずれの場合においても免税措置を受けられる期間は「令和7年(2025年)3月31日まで」になっていることが重要です。
そのため、2022年8月現在において対象となる土地に関して相続登記が完了していなかったり、あるいは免税期間の終了までの間に条件に該当する土地の相続が発生したりした場合、必ず適切な手続きを行って免税措置の適用を受けられるようにしておきましょう。
なお、免税措置が認められれば、本来であれば登録免許税の算出に0.4%の税率がかかるところ、適用後は免税となって登録免許税は発生しません。
免税を受けるにはどうすればよいか?
土地価額が100万円以下の場合において、相続登記の登録免許税の免税措置を受けようとした場合も、やはり免税の根拠となる法令の条項を申請書へ記載した上で提出することが必要です。
該当する内容は「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」となっており、こちらを申請書へ記載して窓口へ提出してください。
当然ながら、記載内容に誤りがあったり、記載することを忘れていたりした場合、免税措置は適用されません。
まとめ
例えば100万円の土地を相続したとして、従来の税率0.4%にもとづいて登録免許税を計算すれば4千円の費用が発生します。しかし、申請書に必要事項を記入して提出するだけでこの負担が免税されるとなれば、積極的に活用していくべきといえるでしょう。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるため、より一層に節税対策として免税期間中の手続きが重視される可能性もあります。
ただし、相続登記の登録免許税の免税措置は書類の不備や申請の誤りなどで適用されないこともあり、不安や疑問点があれば専門家へ依頼して任せることも無難です。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。