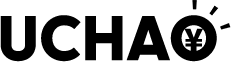公開日: |更新日:
共有持分の割合と計算方法・注意点
マンションの購入や相続時など、住宅取得時には、共有持分の割合「持分割合」をどのように決めるかが重要なポイントになります。適正な割合にしなければ、損をしたりトラブルが起きたりする可能性があるため注意が必要です。
ここでは、共有持分の割合の決め方や計算方法、注意点を紹介します。
共有持分の割合の決め方と計算方法
共有持分の割合の決め方は、ケースによって異なります。たとえば、不動産を共有名義で購入する際は出資割合に合わせて決めるのが一般的です。
一方、相続などで取得する際は法定相続分が基準となります。自由に決めてしまうと、贈与税がかかってしまう可能性があるため注意しましょう。
不動産を共有名義で購入する場合
夫婦や親子など、2人以上で資金を出しあって不動産を購入する際は、基本的に負担額によって持分割合が決められます。住宅ローンがある際は、「住宅ローンを含めた支払い金額 = 負担額」です。
持分割合は、以下の計算式で求められます。
- 持分割合 = 負担額(住宅ローン含む)÷ 不動産の購入代金
たとえば、3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円負担、妻が1,000万円負担すると、それぞれの持分割合は次のようになります。
- 夫の共有持分の割合…2,000万円 ÷ 3,000万円 = 3分の2
- 妻の共有持分の割合…1,000万円 ÷ 3,000万円 = 3分の1
持分が割り切れない場合
持分が割り切れないケースも考えられます。計算で割り切れない場合は端数を調整しましょう。
たとえば、先ほどの3,000万円の住宅を夫が2,300万円、妻が700万円負担するとしましょう。割り切れないので端数を整えます。
- 夫…2,300万円 ÷ 3,000万円 = 0.766… → 0.77%へ
- 妻…700万円 ÷ 3,000万円 = 0.233… → 0.23%へ
夫の持分は77%・妻の持分は23%と、きれいに調整できました。ただし、調整によって持分が増減すると、税務上では「贈与があった」とみなされます。
上記ケースでは、妻から夫への贈与があったことになりますが、年間110万円までの贈与であれば非課税になるため、贈与税はかかりません。持分割合の調整をする際は、110万円を超えないよう注意しましょう。
親から資金援助があった場合
親からの資金援助には、3つの方法があります。
- 資金をもらい夫婦の資産にする「贈与」
- お金を借りて購入資金に充てる「借入」
- 一緒に不動産を購入する「共同出資」
贈与や借入で資金援助を受ける際は、資金を負担額に合算できます。たとえば、夫の親から援助を受けたときは、夫の負担額と合わせるとよいでしょう。
とはいえ、贈与は金額によって贈与税が発生する可能性があります。借入では、親への返済が発生します。どちらも忘れないようにしましょう。
共同出資では、親も共有者になるため、持分割合を持つことになります。夫婦それぞれの父親から共同出資をしてもらった場合は、夫婦 + 夫の父親 + 妻の父親の合計4人が持分割合を持つということです。
それぞれの出資額に応じて持分割合を計算しましょう。
共有持分を相続する場合
遺産相続時など、親が亡くなった際に配偶者と子どもが不動産を共有するケースでは、持分割合は法定相続分に応じて決める、または遺産分割協議によって決める方法があります。
法定相続分に応じて決める場合
法定相続分とは、故人の財産を継承するにあたって民法に定められた相続割合のことです。法定相続人の順位によって、法定相続分は異なります。
たとえば、夫が亡くなり、配偶者と子ども2人が不動産を相続したとしましょう。このケースでは、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつ共有持分を取得することになります。
遺産分割協議によって決める場合
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で分割割合を決めることもできます。たとえば、上記のケースと同様に夫が亡くなり、法定相続人は配偶者と子ども2人だとしましょう。
夫の財産である自宅と預貯金を分割する場合、民法では配偶者が2分の1、それぞれの子どもが4分の1ずつの割合で相続します。自宅は物理的に分割できないため、配偶者と子ども2人の共有状態となります。
しかし、子どもがそれぞれ独立し、持ち家を保有しているケースも珍しくありません。そうなると、「実家の共有持分を相続しなくていい」と考えるかもしれません。
そこで、遺産分割協議で話し合い、全員が合意すれば配偶者が単独で自宅を相続し、子ども2人で預貯金を相続する、といった分割も可能になります。
共有持分を決める際の注意点
共有持分は、適当に決めてしまわないようにしましょう。「夫婦で折半ね」と出資額や返済負担額を考慮せず決めてしまうと、贈与税が課される可能性や、住宅ローン控除額が減らされてしまう可能性があります。
また、住宅ローンの種類も確認が必要です。夫婦で住宅ローンを組むパターンには、連帯保証型・連帯債務型・ペアローンがあります。
このうち、連帯保証型では、債務者が住宅ローンの単独名義となるため、連帯保証人には持分は認められません。夫婦双方が持分を取得したい際には、連帯債務型、もしくはペアローンを選択するようにしましょう。
こちらのページでは全国に対応しているおすすめの共有持分買取業者を紹介しています。共有持分の割合でトラブルにならないためにも、専門業者に相談してみるのも1つの手段です。

2016年:宅地建物取引士資格取得
不動産会社で賃貸物件の仲介、地主様の土地活用、マンションの管理やそれらに関する維持サポート等を行うかたわら、2018年よりライターとして活動をスタート。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。