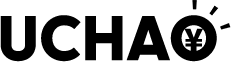公開日: |更新日:
不動産の共有者が死亡した際の相続人は?
共有者に相続人がいるケース
不動産を誰かと共有しているとして、その共有者が亡くなった場合、共有者に法定相続人がいたり、遺言によって共有持分を相続させたい相手が指定されていたりすれば、通常の相続と同様に共有持分は相続人へ受け継がれます。
そして相続が完了した後は、自分と、新たに共有持分の権利者となった相続人とで対象の不動産を共有していくことになるでしょう。
なお、共有者に複数の法定相続人がいた場合、共有持分は相続財産としてそれぞれの法定相続人へさらに分配されます。そのため、状況によっては不動産の共有者の人数が増えてしまうケースもあります。
共有者の法定相続人とは?
法定相続人とは民法によって相続人として規定されている人物であり、一般的には配偶者や子供が考えられます。被相続人に配偶者や子供がいない場合、その親や兄弟姉妹が法定相続人として権利を持つこともあります。
なお、遺言によって「全ての財産を第三者に譲渡する」といった被相続人の遺志があったとしても、法定相続人には遺留分として一定の財産を相続する権利があることも重要です。
共有者に相続人がいないケース
共有者に法定相続人がいない場合、状況によっては問題が複雑化する可能性があります。
相続人不在の状態とは?
不動産を共有していた人物に、法定相続人や遺言によって指定されている遺贈先が存在していた場合は前述した通りです。しかし特定の相続人が存在しない場合、「相続人不在の状態」として対処しなければなりません。
なお、相続人不在の状態になるケースとして、まずは共有者に妻や子供、親、兄弟・姉妹といった縁故者が誰もいない場合が想定されます。またその他の可能性として、相続人は存在したものの、7年間以上の行方不明などで居場所が確定されず、生存確認ができず法律上「死亡している」と見なされる場合もあります。
ただし、相続人の死亡によって相続権が代襲相続された場合、相続人不在の状態にはなりません。
一見すると相続人不在の状態であったとしても、実際には相続人が存在しているといったケースもあり、不確定な要素が少しでも考えられる場合は専門家へ相談することが無難です。
相続人不在の状態が認められれば民法の規定に従って共有持分が扱われる
相続人不在の状態が発生した場合、共有持分は民法255条、もしくは民法958条の3の規定に従って取り扱われます。
どちらのケースに相当するかで共有持分の帰属先が変わるため、慎重に考えることが大切です。
民法255条が適用された場合
民法第255条では、不動産の共有者について「相続人不在の状態」が発生した際に、「その持分は他の共有者に帰属する」という規定が記されています。つまり、例えば自分ともう1人の人物で不動産を共有しており、その共有者に相続人が存在しない場合、不動産は全て自分のものになるということです。
ただし、民法255条が適用される前に、条件次第では「民法958条の3」の規定が適用されることもあります。同規定が適用された場合、全くの第三者が新しい共有者になることもあるため注意しなければなりません。
民法958条の3が適用された場合
民法958条の3では以下のような規定が決められています。
- 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
- 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
つまり、不動産の共有者に相続人が存在しない場合であっても、「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」が家庭裁判所に対して適正に申立を行えば、特別縁故者として共有持分などの相続対象になり得るという決まりです。
ただし、特別縁故者が申立を行える期間もまた定められており、特別縁故者が存在していたとしても、期間内に特別縁故者が申立を行わなければ民法255条が適用されます。
民法255条と民法958条の3では後者が優先される判例
それでは特別縁故者が民法958条の3の規定に従って申立を行った場合、不動産の共有持分の帰属先はどうなるのでしょうか。
民法255条に従った場合、共有持分は現在の共有者に帰属されます。しかし民法958条の3に従った場合、共有持分は特別縁故者のものとなります。
平成元年11月24日の最高裁判所の判例(事件番号:昭和63(行ツ)40)によれば、民法958条の3と民法255条が対立した場合、特別縁故者が優先的に共有持分の帰属先になるということが認められました。
つまり、もしも特別縁故者が存在して、申立が行われた場合、被相続人が所有権を有していた共有持分の一部または全部が特別縁故者に受け継がれるということです。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。