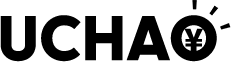公開日: |更新日:
相続登記の手順
不動産を所有している方が亡くなった場合、不動産の名義変更を行う必要があります。名義を変更することを相続登記と言い、相続登記を自分で行うべきか、専門家に依頼するのか悩むこともあるでしょう。このページでは相続登記の手順などを分かりやすく紹介していきます。
相続登記は自分でやるべき?
自分で行うことを検討しても良いケース
続登記というと、専門家に任せる必要があると思われがちです。しかし自分で行えるケースもあります。
- 相続人が配偶者と子供だけ一般的な相続パターンにはなりますが、たとえば夫が亡くなり、妻と子供だけが相続人となるケースです。このパターンであれば必要となる戸籍も限定され、複雑な手続きもほとんどないでしょう。
- 手続きに行ける時間がある手続きするためには法務局や役所などに足を運ばなければなりません。それらは基本的に平日のみの対応になるため、平日は仕事などで忙しいという場合は手続きを行う時間がないでしょう。そのため平日時間が取れるということも条件になります。
- やる気があるある意味、やる気があるかどうかが一番大切です。戸籍をチェックする、税金の計算をする、役所に何度も行くなど、時間的にも肉体的にも精神的にも労力がかかります。それでも頑張れる!というモチベーションがなければ、専門家に依頼した方がいいでしょう。
専門家へ依頼することを検討すべきケース
相続登記を専門家に依頼した方が良いというケースもあります。それは相続に対し、複雑な問題を抱えている場合です。トラブルを避けるためにも専門家に任せ、適切な手続きを踏んでもらいましょう。
- 兄弟間での相続や代襲相続などのケース兄弟間での相続などのケースだと必要となる戸籍の数が多くなり、戸籍の収集が非常に大変になってきます。配偶者や子供の相続であれば相続人の現在の戸籍や被相続人の出生・死亡の戸籍が必要ですが、兄弟間であれば被相続人の親や状況次第では祖父母の死亡記載がある戸籍も必要です。そのため戸籍を集めるだけでもストレスになってしまうでしょう。
- 被相続人の先祖名義ままの不動産登記のケース被相続人名義だと思い込んでいた不動産物件が、被相続人の親や祖父母になっているケースもよくあります。この場合は登記手続きだけでなく、専門的な知識が必要とされ、ケースによっては戦前の旧民法もかかわってくることもあるでしょう。そのため、こういったケースで法律の知識がなく、対処するのは困難です。
- 相続人同士が不仲、または疎遠のケース相続を行うためには、相続人で様々な話し合いをしなければなりません。不仲や疎遠であれば、連絡を取るのも難しいため、専門家のサポートを受けた方が楽でしょう。
- 遺産分割に関する協議をしたいケース代償分割や換価分割などの複雑な分割方法を行う場合には、非常に高い知識が必要となります。そのため専門家のサポートがなければ、適正な分割を行うのは難しいでしょう。
- 素早い登記が必要なケース相続する不動産の売却がほぼ決まっており、取引予定までに相続登記を終えなければいけないケースも専門家に依頼した方がいいでしょう。
- 必要な書類が入手できない登記記録上の住所次第では、戸籍附表が必要になってきますが、この書類が役所の都合で入手できないことも。この場合は、法務局と提出する書類について打ち合わせを行わなければならず、専門家に任せた方が安心です。
- 遠方に住んでいるケース相続する不動産が居住している場所から離れていると、不動産の調査や法務局の申請などの手続きに煩わしさを感じるでしょう。専門家に依頼すれば、スムーズに手続きを終えることができます。
相続登記を自分でやるメリットはある?
そもそも不動産の相続名義を相続人が自分で行う必要性があるのでしょうか。ここでは、相続人が相続登記を自分でやるメリットや理由についてまとめています。ポイントをきちんと把握した上で、相続登記を自分で行うかどうか決めることが大切です。
メリット
相続登記を自分でやるメリットは、税理士に依頼して支払う報酬を節約できるという点です。加えて、自分が不動産の登記を行うことで、どのような手順で申請を進めれば良いのか経験や知識として得られるということもメリットとして挙げられます。
司法書士へ支払う報酬は、相続登記の相談だけであっても数万円単位で発生し、さらに相続人調査や必要書類の用意といった作業も依頼すればどんどんと高額になっていきます。
言い換えれば、相続人の数が少なかったり、相続人同士の関係が複雑でなかったりすれば、相続登記もスムーズに進めやすくなるため、そもそも自分でやるデメリットが薄くなるといった可能性も重要です。
デメリット
相続登記を自分でやるデメリットは、様々な準備や手続きをやるために相応の費用や労力、時間が発生してしまうという点です。相続登記では書類を用意するために役所へ出向いたり、相続不動産の価値を改めて調査したり、または申請書を作成するといった作業を行います。
適切に申請を行えたとしても相応の手間や時間が発生する上、書類に記入漏れなどの不備があれば再提出しなければならず、相続登記が完了していない期間が長引けば権利関係がややこしくなる恐れもあるでしょう。
司法書士へ相続登記を依頼するコストは、自分で申請を進める上で発生するリスクを回避するための費用として考えることが重要です。
相続登記における2つの方法
相続登記を行う場合、大きく個人所有の「単独登記」と、不動産を複数人で共有する場合の「共有登記」の2種類の方法があります。
ここでは単独登記と共有登記の違いについてポイントをまとめました。
単独登記
単独登記とは、文字通り相続不動産を1人の相続人が引き継いで登記するパターンです。所有者が1人だけになっているため、申請に必要な書類は所有者の分だけでよく、手続きに関しても所有者が自分のペースで行えることは見逃せません。
また、相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたり、不動産会社などへ相続不動産を売却して現金化したりと、不動産の活用について自分の考えて決められるといったことも重要です。
単独登記になるケースとしては、そもそも相続権を有する人物が1人だけしかいなかったり、または遺産分割協議によって相続不動産を特定の相続人が1人で所有するという話になったりした場合が考えられます。
共有登記
共有登記とは、複数の相続人で相続不動産を共有し、その内容に従って相続登記を行う方法です。共有登記にはそれぞれの共有者が対象の不動産に関して所有する割合(共有持分)が明記されていなければならず、共有登記の前にきちんと互いの共有持分について話し合いが完了していなければなりません。
また、仮に遺産分割協議では共有持分の話し合いがスムーズに行われたとしても、共有者が亡くなればその所有権は改めて相続されてしまうため、将来的に見ず知らずの第三者が共有者として参加しているといったリスクもあります。
相続登記の手順
手順1.相続物件を特定する
まず相続を行う不動産の特定を行うことが大切です。不動産の特定を行わなければ、スムーズに相続を終えることができないでしょう。
相続する不動産を特定するために「固定資産税課税明細書」をチェックするのが必要になってきます。この書類には課税の対象者が保有している不動産が記載されており、この明細書をみれば被相続人が所有している不動産の情報を把握できるでしょう。
もし課税明細書がないのなら、役所で不動産の「名寄帳」を請求してください。これは不動産リストが書かれてある書類なので、被相続人の所有不動産を簡単に把握できます。
手順2.被相続人の戸籍謄本などの取り寄せ
不動産の情報を把握したら、次は相続に関わる方の戸籍の書類や住民票の除票などを用意します。この取り寄せ自体は、非常に時間を要してしまうことがあるので、早めに行うようにしましょう。
- 被相続人の戸籍謄本など被相続人の出生から死亡まで記載された戸籍謄本を用意します。妻や子の有無などを確認するために使用するもので、もし遺言状による相続であれば死亡時の戸籍謄本だけで構いません。
被相続人の本籍地が書かれた住民票で、最後の本籍地を確認し、その本籍地で被相続人の戸籍謄本を用意するという流れです。 - 被相続人の除籍謄本と改製原戸籍戸籍謄本に記載されている戸籍事項の欄に「転籍」と記載されていれば、従前本籍のある役所で除籍謄本を取得していかなければなりません。戸籍自体には、ひとつ前の本籍地しか書かれていないため、このステップを何度も繰り返すケースもあります。
さらに戸籍事項の欄に「戸籍改製」とある場合は、同じ本籍地で改製の前段階の「原戸籍」を取得しなければなりません。 - 被相続人の住民票(除票)住民票の除票は、被相続人の最後の居住地で発行してもらう書類となります。必ず本籍地を記載したものが必要ですが、保存されている期間は削除された年から5年間となるので注意しましょう。たとえば相続する不動産取得時の住所が記載されないケースも。この場合は登記上の住所とのつながりを証明しなければなりません。ただ5年以上経過していれば、住民票の除票だけでは証明できないため被相続人の本籍地で「戸籍の附表」を取得してください。
手順3.相続人の確定・書類取り寄せ
被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを確認したうえで、相続人を確定します。この際、家族が全く把握していない相続人がいるケースもあるので、しっかりとチェックしておきましょう。相続人が確定すれば、相続人の戸籍謄本や住民票を用意します。この場合、住民票は不動産の名義人になる方だけで構いません。
また被相続人が死亡したタイミングで、相続人が生きていたことを証明する必要があり、もし複数の相続人がいる場合は、それぞれで取得してください。もし遺言書に従って相続するなら、相続人の戸籍謄本だけが必要になってきます。
手順4.遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続登記を行う際、被相続人の財産をどうやって分割し、誰が取得するのか、相続人で話し合ったうえで所定の方法で「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。この書類を申請する際に添付する必要があります。また相続登記の遺産分割行書は、相続する財産のすべてに関して記載されている必要はないため、対象の不動産だけが記載されたものでも十分です。
遺産分割協議書とは
相続人が法定相続分で分けるのではなく、遺産分割協議によって割合を決め、不動産相続を行う場合に「遺産分割協議書」の作成が必要になってきます。この書類自体に決められた形式はなく、記載しなければならない事項だけが決まっているだけです。
また遺産分割協議書には実印を押さなければなりません。実印であることを証明するために相続人全員の印鑑証明書も必要となるので、必ず各自で取得してもらいましょう。また遺産分割は、法定相続人が一人でも欠けてしまうと無効になってしまいます。そのため必ず法定相続人全員が揃っているのか確認してください。
手順5.申請書の作成・申請
必要となる戸籍謄本などを集め、相続人の確定、遺産分割協議書の作成が完了すれば、次は登記の申請という流れになります。登記するためには必ず「登記申請書」が必要となるので、作成しなければなりません。相続登記の申請を行うための書類は法務局の公式サイトで、ひな形があるため簡単にダウンロードし仕様することが可能です。その書類を使う方が比較的スムーズでしょう。
固定資産評価の証明書
不動産の相続登記をする際、「固定資産評価証明書」または「課税明細書のコピー」が必要になってきます。これらの書類は登録免許税を算出する際の固定資産税評価額をチェックするためにも必要です。
また亡くなった年度の書類ではなく、相続登記を申請する年度の書類が必要になるので注意しましょう。申請するタイミングに合わせて、一番新しいものを用意してください。
課税明細書は、自宅に届く固定資産税の納税通知書に同府されている書類です。もし課税明細書を紛失していても、相続不動産のある自治体から固定資産評価証明書を取得すれば問題ありません。ただ書類を発行するための手数料や必要となる書類が異なるため、相続不動産のある自治体の公式サイトで、どのような書類が必要なのかを確認したうえで手続きを進めてください。
収入印紙
相続登記を行う際の登録免許税を納付する際に必要になってきます。
「登録免許税=固定資産評価額×0.4%」
上記の計算方法で求めることができ、固定資産評価額とは課税明細書や固定資産評価証明書に書かれてある評価額になります。評価額は1000円未満を切り捨てし、求めた登録免許税に関しては100円未満が切り捨てとなるので間違えないようにしましょう。
原本還付のための書類
登記を完了したあとで添付した書類を返却してもらうことができます。この手続きを原本還付と呼び、この手続きをしなければ戸籍謄本などの書類が返却してもらえないため注意してください。銀行などで相続手続きをする際も添付した書類が必要となるため、できれば原本還付は行った方がいいでしょう。
- 相続関係説明図戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本に関しては、相続関係説明図を作成し、提出すると原本の返却が可能です。
相続関係説明図や書類のコピーを、まずは原本とまとめて提出します。その際は割印などが必要になってくるので、正しい方法で提出するように適切な方法を必ず法務省の公式サイトなどで確認してください。間違えてしまうとスムーズに手続きができないので注意しましょう。 - 原本還付を希望する書類のコピー 基本的に戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本以外の書類に関しては、原本と一緒にコピーを提出すれば原本は返却してもらえるでしょう。ただコピーの全てに申請者の住所や氏名、原本還付を求める旨を記載したうえで押印する必要があり、また場合によっては契印も必要となってきます。
- 返信用封筒原本を郵送で返却した場合は、切手を貼った返信用封筒が必要になってきます。もし窓口で返却書類を受け取るなら、返信用封筒は必要ありません。
法務局に申請
すべての書類がきちんと揃ったら、法務局で申請をします。この際、相続不動産を管轄している法務局で申請を行う必要があるため、管轄がどこなのかは法務局の公式サイトで確認しましょう。
- 法務局で申請する法務局まで足を運び、直接申請する方法があります。この方法であれば、修正があったとしてもスグに対応できるといったメリットがあるでしょう。申請書・添付書類・収入印紙・申請書に押した印鑑を用意してください。
- 郵送で申請する管轄の法務局に郵送して申請することも可能です。この場合は書留郵便もしくはレターパックプラスで送るようにしましょう。管轄している法務局が遠い場合や交通手段がない場合にオススメです。
- オンラインで申請するオンラインによる申請にも対応しており、法務省の公式サイトで手順などが詳しく解説されています。ただ登記のために専用のソフトをインストールする、公的認証サービスを活用し電子証明書を取得するなどの手間がかかり、パソコンに詳しくないと難しいかもしれません。またオンラインで申請したとしても、添付書類は2日以内に郵送または持参しなければならず、すべての手続きがオンラインで完結できるわけではないので注意してください。
申請後の手続き
申請し相続の登記が完了するまで、およそ1週間から10日要します。無事に登記完了の予定日が来たら、法務局に書類を受け取りに行ってください。その際、身分証明書や登記で使用した印鑑が必要になるので、忘れずに持参しましょう。また郵送での受け取りを希望している場合には、登記終了の書類が郵送で届きます。
どうしても登記完了までに時間がかかってしまうので、もし不動産売却などの日程が決まっているのであれば、早い段階で手続きを行うことが大切です。スムーズに手続きを終えるためにも書類などをしっかり確認し、ミスがないように心がけましょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。