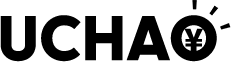公開日: |更新日:
「相続登記」と「所有権移転登記」の違いとは?
不動産を相続した際に行う「相続登記」と「所有権移転登記」にはそれぞれどのような特徴があるのでしょうか。このページでは、相続登記と所有権移転登記の違いや手続きを行う際のポイントなどをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
「相続登記」は「所有権移転登記」のひとつ
相続登記と所有権移転登記はどちらも、不動産相続が発生した際に選択する可能性のある手続きですが、両者は完全に別物というわけではありません。
そもそも「所有権移転」とは、不動産の所有者(所有権)が別の人物へ移ることを意味しており、所有権移転登記とは所有者の変更を公的に示すための手続きです。そして、所有権が移転する原因として不動産相続が発生していた場合、それは相続登記として区別されます。
つまり、様々な理由によって行われる所有権移転登記という枠組みの中に、不動産相続に起因して発生する相続登記も含まれているという仕組みです。
その他の所有権移転登記の種類
相続によって所有権移転登記を行うといったケースの他にも、様々な理由で所有権の移転が発生することがあり、当然ながらそれぞれの理由に応じた所有権移転登記が行われます。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、一般的に注文住宅を新築した場合や、新築の戸建て・マンションといった不動産を購入した際に必要となる登記です。
そもそも新築物件は登記が完了しておらず、公的には誰の持ち物であるのか具体的に定められていないという状態にあります。そこで新築物件を購入した場合は、最初のオーナーとして所有権保存登記を行い、自分に所有権があることを示すという手続きが必要です。
表題登記
表題登記とは、所有権保存登記を行う前段階として必要になる登記です。
所有権保存登記では物件の所有者が誰であるのかを登録することに対して、表題登記では不動産の用途や構造、面積といった情報を公的に登録します。
表題登記を行うことで、不動産の性質や実態が特定され、改めて所有権の登録などへ進むことが可能となります。
抵当権設定登記
抵当権とは、例えば住宅ローンの支払いが困難になった場合などの担保として、金融機関が土地や家屋へかける権利です。
住宅ローンを申し込む場合、担保として自宅などを提示すれば、金融機関はそれに抵当権をかけ、滞納が発生した際などに不動産を差し押さえられるようになります。
抵当権設定登記とは、そういった抵当権が登録されていることを公的に示すための登記です。
相続登記にも3つのパターンがある
不動産相続によって発生する所有権移転登記が相続登記ですが、そもそも不動産を相続する方法として大きく3つのパターンがあります。そのため、まずはケースに応じた相続登記の違いを理解しておきましょう。
遺言書による相続登記
被相続人が生前に遺言書を作成しており、その中で所有している不動産を特定の誰かに相続させるという意思を表明していたとします。そしてそのような場合、法務局で所有権移転登記を行う際には、その遺言書を持って手続きを行うことになります。
こういったケースが遺言書によって発生する相続登記です。
法定相続による相続登記
法定相続とは、あらかじめ法律によって認められている相続権にもとづいた相続です。例えば遺言書が存在しない場合、被相続人の資産や財産は法律によって定められている割合に従って各相続人へ分配されます。
また、仮に遺言書がある場合でも、法定相続人には「遺留分」という一定割合の遺産を相続する権利が存在していることがポイントです。そのため、例えば「全ての遺産を特定の誰かに相続させる」という遺言書があったとしても、遺言で指定されていない相続人は遺留分を遺産として相続することができます。
このような法律の定めに従って行われる所有権移転登記が、法定相続による相続登記です。
遺産分割協議書による相続登記
法定相続にもとづいた割合や遺留分といったものがあったとしても、実際に1戸建ての住居を物理的に分割して、個々の相続人が所有するといったことは困難です。そのため実際には不動産の一部を共有持分として各相続人が所有するか、あるいは話し合いによって特定の誰かが不動産を相続し、代わりに現金を残りの相続人へ支払うといったことが行われます。
このような話し合いが遺産分割協議であり、協議内容は遺産分割協議書という書面でまとめられます。
遺産分割協議書による相続登記の場合、登記手続きに遺産分割協議書が必要です。
所有権移転登記にかかる費用はどのくらい?
所有権移転登記にかかる費用としては、一般的に「登録免許税」・「必要書類の準備にかかる費用」・「司法書士への依頼料」という3種類が考えられます。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の際に発生する費用です。登録免許税は定額でなく、対象となる不動産の固定資産評価額と税率によって算出されます。
- 登録免許税=固定資産評価額×税率
なお、税率については令和4年度の税制改正によって、令和6年3月31日までの期間中、登録免許税の軽減措置として税率が低くなっていることも重要です。
必要書類の準備にかかる費用
登記には様々な必要書類が発生します。例えば確実に必要とされる書類として「登記事項証明書」がありますが、この取得には法務局照明センターや登記所で発行手数料を支払わなければなりません。
その他にも相続人全員の戸籍謄本であったり、相続人全員の住民票の写しであったりと、様々な書類が考えられるため、自分のケースに応じて考えるようにしてください。
司法書士に依頼する場合にかかる費用
不動産の登記手続き自体は個人で行うことが可能です。しかし相続登記や所有権移転登記は個人が行おうとすれば大変な作業になることも多く、必然的にプロである司法書士へ依頼することは少なくありません。
ただし、司法書士へ登記の代行を依頼する場合、相応の依頼料を報酬として支払う必要があります。
司法書士へ支払う金額は各司法書士が決定できるため、まずは複数の司法書士へ問い合わせてコストメリットの比較検討を行うことも大切です。
まとめ
相続登記と所有権移転登記は本質的に異なるものでなく、いずれにしても不動産相続によって不動産を所有した場合に必要となる手続きです。ただし、どのような理由や経緯で不動産を取得・相続したかによって用意すべき資料や書類が異なることもあります。そのため、これまでに相続登記や所有権移転登記に携わった経験のない人であれば、まずは専門家へ相談したり依頼したりといったことが無難でしょう。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。