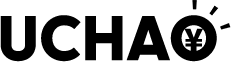公開日:|更新日:
共有持分の土地や家の売却における注意点
共有不動産とは?
共有不動産とは、一つの土地または建物を二人以上が持分を定めて共同で所有している状態を指します。各共有者は自らの持分について単独で登記や譲渡ができますが、不動産全体を売却したり大規模な増改築を行ったりするには共有者全員の同意が必要です。
共有不動産の売却時に注意すべきポイント
法律上の注意点:同意要件と民法の規定
法律上最も重要なのは共有者全員の同意が必要という点です。民法第251条により定められており、不動産全体の売却やその他の「変更行為」(増改築や抵当権設定など)は、共有者全員の同意なしにはできません。一方で、自分の持分だけを売却する場合は、他の共有者の同意を得る必要はなく、民法第206条により単独で処分可能です。しかし、全体売却に反対する共有者がいる場合は売却が進まず、共有物分割訴訟などの法的手段を検討する必要があります。
手続き上の注意点:書類準備と共有者間の調整
必要書類の準備を行います。
- 登記識別情報(昔の権利証)
- 土地は測量図・境界確認書など
- 共有者全員の実印、印鑑証明書、身分証明書、住民票
- 売買契約書に全員の署名・押印
共有者が多い場合や一部が売却に立ち会えない場合は、委任状を取得します。共有者間で売却条件の合意を円滑に進めるため、早期に話し合いを重ね、書類準備と調整を怠らないことがスムーズな売却のポイントです。
税金面の注意点:譲渡所得税・贈与税の取り扱い
譲渡所得税は各共有者の持分割合に応じて計算され、それぞれが納税義務を負います。譲渡所得は売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた利益で、所有期間が5年超なら長期譲渡所得として税率が軽減されます(所得税約15%、住民税約5%)。売却益が出た場合は翌年2月16日〜3月15日の確定申告が必要です。一方、贈与税は共有持分を贈与する際に課されます。売却とは別の税務手続きが必要です。共有名義のため、控除や特例の適用も共有者ごとに判定され、節税対策には各人の所有期間や取得状況を把握しなければなりません。
共有不動産の基礎知識:定義と売却・現金化の可否
共有不動産の定義と特徴
共有不動産とは、複数人がそれぞれ持分を持って所有している不動産のことです。相続や共同購入によって一つの不動産を複数人で共有するケースなどがあります。共有不動産は、所有者全員の同意がなければ不動産全体の売却や処分ができません。自分の持分のみならば、他の共有者の同意なしに単独で売却可能ですが、持分だけの売却は市場での流動性が低く、価格も通常の売却価格より大幅に安くなる傾向があります。また、共有物分割請求訴訟により裁判所を通じて共有状態を解消することも可能ですが、時間と費用がかかります。共有不動産は利用や処分に制約が強いため、関係者間の合意形成が重要です。
売却・現金化の可否と法的制限
共有物の売却は「変更行為」にあたり、民法第251条により全員の同意がないと不動産全体の売却はできません。自己の共有持分のみの売却は、民法第206条で他の共有者の同意なしに単独処分が認められています。しかし、持分のみの売却は市場で買い手が限られ、通常の市場価格より大幅に割り引かれやすいです。合意形成が困難な場合は、共有物分割請求訴訟による共有解消も可能ですが、裁判費用と時間がかかります。
共有持分単独売却の概要
共有持分単独売却とは、共有している不動産全体ではなく、自分が持つ持分部分だけを第三者に売却することを指します。これは民法第206条によって認められており、共有者の同意なしに単独で行うことが可能です。共有持分のみの売却は市場流通性が低く、利用制限が多いため、通常の不動産全体売却に比べて価格が大幅に割り引かれる傾向があります。この売却方法は共有者間の合意が得られない場合や関係が悪化している時の解決手段として用いられますが、共有関係自体は解消されないため利用には制約が残ります。
共有不動産を現金化・売却する方法と流れ
共有者全員の合意による売却方法
共有者全員の合意で売却する方法は、最も一般的かつ有利な方法です。法務局で共有者全員を確認し、話し合いで売却の意思と条件をまとめます。合意が得られたら、不動産業者に依頼して市場価格で売却活動を行い、買主が決まれば売買契約を締結。売却代金は各共有者の持分比率に応じて分配されます。共有物の売却には全員の同意が必須で、一人でも反対すると売却できません。だからこそ、事前の合意形成が最も重要なポイントです。
自分の持分のみを第三者に売却する方法
民法第206条に基づき、自身の持分については他の共有者の同意なしに自由に処分可能です。売却手続きとしては、まず持分の価格査定を行い買い手を探しますが、共有持分は単独で利用・処分が難しいため買い手を見つけるのが困難で、価格も通常の不動産に比べて大幅に低くなる傾向があります。売却の通知義務はありません。第三者に購入されると共有関係が変わる可能性があるため、親族間などではトラブルを避けるため慎重な対応が求められます。
買取業者/リースバックを利用した現金化手段
専門の共有持分買取業者に売却を依頼すると、一般的な売却より早く最短数日で現金化が可能で、仲介手数料も不要です。特に共有者間の合意形成が難しい場合や急な資金ニーズに対応できます。一方で、買取価格は市場価格より低くなることが多いです。また、リースバックは、不動産を買取業者に売却した後も、賃貸としてそのまま住み続けられる仕組みで、住環境を変えずに現金を得られます。
売却の流れ:手続きステップと必要書類
- ステップ1:共有者全員の合意形成を行い、売却方針や最低売却価格を決定
- ステップ2:不動産会社へ査定依頼をし、媒介契約を締結
- ステップ3:買主が見つかれば売買契約を締結
- ステップ4:代金の決済後、司法書士に依頼して所有権移転登記を行い、売買が完了
主な必要書類は住民票、登記識別情報通知(権利証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書、共有者全員の同意書、土地測量図などです。
共有不動産が生まれる典型例:ケース別解説
相続による共有発生ケース
相続による共有発生は共有不動産が生まれる典型的なケースです。例えば、亡くなった親の不動産を複数の相続人が法定相続割合で分割相続すると、その不動産は「持分」を共有する形で相続されます。この場合、兄弟姉妹や配偶者がそれぞれの持分を所有し、共有不動産として登記されます。ただし、共有状態では共有者全員の同意なしには不動産の売却や処分が困難となり、後に関係悪化や意思不一致が原因で処分が滞るトラブルも多発します。また、共有者のうち誰かが亡くなり二次相続が重なると、共有者がさらに増え、複雑化することがあります。
離婚による共有発生ケース
夫婦が婚姻中に取得した土地や建物などが、離婚時の財産分与で完全に清算されず、離婚後も夫婦双方の持分を共有したまま残るケースです。例えば、住宅ローンを夫婦で組んだり、妻の特有財産が一部出資されたりした不動産は、離婚後も所有権が共有のままになることがあります。共有者全員の同意なしに売却や処分が難しく、片方が住み続けることで明渡し請求の法的制限が生じることもあります。
贈与による共有発生ケース
贈与による共有発生も共有不動産が生まれる典型例です。所有者が自分の持分の一部または全部を第三者に贈与することで、新たに共有関係が生じます。例えば、父親が所有する土地の一部を子どもに贈与すると、父親と子どもが共有者となり不動産が共有状態になります。法的には他の共有者の同意は不要です。しかし、贈与後は土地の管理や利用について共有者間で協議が必要となります。また、贈与税は贈与された持分の価格に応じて課税されるため、税務面の確認も重要です。
売りたくても売れない現実と心理的ストレスの解説
共有不動産が売れない最大の理由は、共有者全員の同意が必要なため意思決定が難航することにあります。売却を望む共有者と居住や運用を希望する共有者の意見対立で、売却自体が止まるケースが多いです。また、共有者の権利関係が複雑なため、買い手側もトラブルを避けるため敬遠しがちで、市場の流通性や価格も低下します。このような売れない現実は、共有者間の交渉疲れや将来の処分不透明感から心理的ストレスを増大させ、関係悪化や精神的負担を引き起こすことも少なくありません。
共有持分買取業者を活用するメリットとリスク
迅速な現金化と交渉不要のメリット
共有持分買取業者を活用する最大のメリットは、共有者全員の同意が得られなくても自分の持分を単独で迅速に現金化できる点です。通常の売却は共有者間の合意調整が必要で時間がかかりますが、買取業者なら面倒な交渉や手続きが不要。早ければ数日で現金化が可能です。また、買い手を自分で探す手間も省けるため、急ぎの資金調達に適しています。
専門業者利用による流動性確保のポイント
共有持分買取業者を利用することで、通常難しい共有持分の流動性を高め、迅速な現金化が可能になります。専門業者は共有持分の市場ニーズや権利関係に精通しており、一般市場では買い手が見つかりにくい持分でも買い取りやすいため、売却がスムーズに進みます。共有者間の合意が得られない場合でも、自分の持分だけ売却できる点が大きなメリットです。
買取リスクとトラブル事例
買取価格が市場価格より大幅に低くなる場合が多いことには注意が必要です。業者は権利関係の複雑さや流動性の低さを考慮し、割安で買い取るため、期待した売却額にならないことがあります。また、契約内容や説明が不十分だと、後々費用請求やトラブルに発展するケースも報告されています。例えば、買い叩きや契約解除時の違約金請求などが問題になることもあるため、複数社の査定比較や専門家の意見を取り入れ、慎重に契約条件を確認することが重要です。
信頼できる買取業者の選び方
会社の信頼性・実績確認のポイント
信頼できる共有持分買取業者を選ぶ際は、宅地建物取引業の免許を保有しているかの確認が重要です。免許番号が明示されているか、宅建士など有資格者が在籍しているかをチェックしましょう。また、過去の買取実績や取引件数を公式サイトや資料で確認することも信頼性を測るポイントです。インターネットの口コミや評判を複数の情報源で調べ、実際の利用者の声を参考にします。問い合わせ対応の誠実さや説明の丁寧さ、契約内容の明確さも見逃せません。複数業者を比較し、条件や対応力を総合的に判断することが安心して依頼するための基本です。
対応エリアと査定スピードの比較
対応エリアの広さと査定スピードを比較することも重要です。対応エリアが全国または自分の不動産所在地をカバーしている業者を選べば、スムーズに取引が進みます。地方の物件や特殊な共有持分でも対応可能な業者は希少価値が高いです。また、査定スピードの速さも要チェックポイント。最短即日や1営業日で査定価格を提示できる業者は、急な資金ニーズにも迅速に対応してもらえます。
査定価格と手数料の見極め方
持分の買取価格は市場価格の3割〜5割程度に下がることが一般的です。複数の業者から査定額を取得して、査定が高い業者を選ぶことで、できるだけ有利な売却を実現できます。一方、手数料や諸経費が明確でないと、実際の手取り額が減るリスクがあるため、契約前に費用の内訳を確認しましょう。仲介手数料が不要な買取業者もありますが、その他の隠れた費用に注意が必要です。透明性の高い説明をする業者を選びましょう。
トラブル回避のための事前確認事項
まず宅地建物取引業の免許や買取実績をチェックし、共有持分の扱いに慣れた専門業者か見極めます。次に、複数社に査定を依頼し、価格の相場感を把握しましょう。加えて、弁護士と連携しているか、法的サポート体制の有無も確認してください。また、契約内容は細部まで丁寧に確認し、隠れた費用や違約金条項がないか注意が必要です。口コミや評判も複数の情報源で調べ、誠実で丁寧な対応の業者を選ぶことで、売却後のトラブルリスクを大幅に軽減できます。
おすすめ2選
共有持分買取はスピードが鍵。
全国どこでもすぐ駆けつけてくれるフットワークの軽い会社であれば、
地元だけではなく、全国つつうらうらの様々なケースに対応してきているので、
あなたのケースにもきっと対応できるはず!

画像引用元:ワケガイ公式HP(https://wakegai.jp/)
- 買取最小金額実績
- 390万円
- 一括支払い可能額
- 最大
3億円
- 現金化スピード
- 最短即日

画像引用元:ハウスドゥ名駅店公式HP(https://housedo-meieki.com/kyouyu-mochibun/)
- 買取最小金額実績
- 600万円
- 一括支払い可能額
- 2億円
- 現金化スピード
- 最短2日
選定基準:
2023年8月4日時点、「共有持分 買取 業者」「共有持分 買取 会社」でGoogle検索をした際に公式HPが表示された上位49社を調査。
その中から、「全国対応可」と公式HPに記載があり、かつ
1,000万円以下の少額の物件の買取実績があり、1億円以上の高額物件も買取が可能な2社をピックアップ。